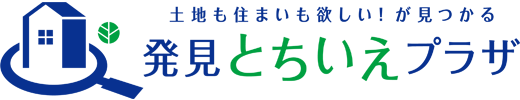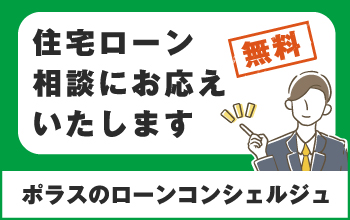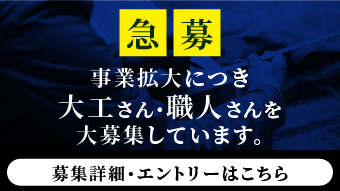【2025年】注文住宅の補助金・助成金完全ガイド!減税制度や活用時のポイントも解説

2025.5.27.
- 注文住宅
この記事では、注文住宅で使える主な補助制度と、それぞれの要件や注意点などをわかりやすく解説します。制度の違いやポイントなどを理解し、もっとも効果的な補助金の活用方法を見つけるための参考にしてください。
※本記事は2025年5月13日時点の内容に基づいています。最新の情報は必ず公式サイトなどでご確認ください。
注文住宅に使える国の補助金制度一覧【2025年版】
注文住宅を建てる際には、国の補助金制度を活用することで、初期費用の負担を大きく軽減できます。
2025年度に利用可能な主要な補助金制度は以下の3つです。
・子育てグリーン住宅支援事業
・ZEH補助金
・給湯省エネ2025事業
どのような制度なのか、順番に紹介していきます。
子育てグリーン住宅支援事業
子育てグリーン住宅支援事業は、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネ性能の高い住宅の取得を支援する制度です。とくにエネルギー価格などによる物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯などに対し、住宅取得の経済的負担軽減を目的としています。
なお、2025年度からは、より高性能なGX志向型住宅については、すべての世帯が対象となりました。
※2 若者夫婦世帯:令和6年4月1日時点で夫婦のいずれかが39歳以下である世帯
※3 古家の解体撤去をともなう場合は20万円が加算される
本制度で対象となる住宅は、性能に応じて次の3種類に分かれています。それぞれの基準を理解することで、自分に合った補助額や住宅グレードを選びやすくなります。
詳細は公式サイトからご確認ください。
子育てグリーン住宅支援事業
ZEH補助金
ZEH(ゼッチ)とは、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略語です。具体的には、断熱性能の強化や高効率設備の導入によって、住宅の一次エネルギー消費量を大幅に削減し、太陽光発電などの創エネ設備で年間のエネルギー収支を実質ゼロにする住宅を指します。
こうしたZEH仕様の住宅を新築する際に、国の補助を受けられるのが「ZEH補助金」です。
補助を受けるには、建築する住宅がいずれかのZEH区分に該当していることが前提となるため、事前に自分の計画がどのグレードに適合するのかを確認しておくことが重要です。また、登録されたZEHビルダー・プランナーを通じて申請する必要がある点にも注意しましょう。
詳細は公式サイトからご確認ください。
令和7年度 戸建てZEH
給湯省エネ2025事業
給湯省エネ2025事業は、エネルギーの使用量が多い「お湯まわり」の省エネをサポートする制度です。高効率な給湯器の導入に対して補助金が出る仕組みで、光熱費の節約につながるだけでなく、地球環境にもやさしい暮らしを後押ししてくれます。
新築に際してエコキュートやハイブリッド給湯器の設置を検討している方にとっては、活用しやすい制度といえるでしょう。
戸建て住宅で導入する場合、最大で2台まで補助が受けられるため、浴室とキッチンで設備を分けて設置したいケースでも対応できます。補助対象の機種や設置条件には細かな規定があるため、事前に登録事業者とよく相談しながら進めましょう。
詳細は公式サイトからご確認ください。
給湯省エネ2025事業
注文住宅を建てる自治体の補助金・助成金制度もチェック
ここまで紹介してきた国の補助金制度に加えて、各自治体でも独自の補助や助成金制度を設けているケースがあります。省エネ住宅の促進や子育て支援、定住促進など、自治体ごとに目的は異なりますが、条件を満たせば数十万円単位の支援が受けられることも珍しくありません。
関東圏の制度を一部紹介します。
■注文住宅で活用しやすい自治体補助制度の例
なお、自治体の制度は変更が多く、補助額や条件も年によって異なるため、最新情報の確認が不可欠です。まずは各自治体のホームページや窓口で確認し、不明点があれば建築会社に相談するのもよい方法です。地元の制度に詳しい会社であれば、申請サポートを受けられる場合もあります。
ポラスの「発見とちいえプラザ」では、埼玉県を中心に、東京都、千葉県、茨城県での補助金制度を活用しての家づくりをお手伝いしていますので、お気軽にご相談ください。
注文住宅で使える減税制度も活用しよう
住宅購入時のコストを抑えるには、補助金だけでなく、税金の優遇制度も見逃せません。ここでは、注文住宅を建てる際に活用できる主な減税制度を紹介します。制度ごとに条件や申請方法が異なるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。
住宅ローン控除(減税)
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できる制度です。対象となる住宅の条件によって、以下のように控除額が変動します。
共働き夫婦がペアローンを組む場合、それぞれに控除が適用される可能性があり、活用次第で節税効果は大きくなります。
一方で、合計所得金額は2,000万円以下とされており、所得が一定以上あると控除額が頭打ちになることもあるため、事前の試算が重要です。
その他の諸条件・詳細については以下からご確認ください。
住宅ローン減税(国土交通省)
不動産取得税の軽減
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される地方税です。新築住宅には以下のような特例が適用され、課税標準の控除や税率の引き下げが受けられます。
これらの控除により、課税対象額が大幅に減り、実際の納税額を大きく抑えることが可能です。条件を満たせば、税額がゼロになるケースもあります。
その他の諸条件・詳細については以下からご確認ください。
不動産取得税に係る特例措置(国土交通省)
登録免許税の軽減
登録免許税は、不動産登記をする際に課される国税です。新築住宅については、以下のような軽減措置が用意されています。
どちらの制度も「自動で適用されるわけではない」ため、忘れずに申請することが大切です。とくに取得時期や申告期限を過ぎると適用されなくなるため、建築会社や司法書士と連携して早めの準備を心がけましょう。
その他の諸条件・詳細については以下からご確認ください。
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(国土交通省)
贈与税の非課税の特例
親や祖父母など直系尊属からの住宅取得資金の援助については、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる特例が設けられています。住宅の性能によって非課税限度額が異なり、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税になります。
ただし、この特例を利用するには贈与を受けた翌年に確定申告が必要であり、「申告しなくても大丈夫」と誤解してしまうと適用されません。
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることなど要件もあるため、利用を検討する場合は早めに内容を確認し、計画的に進めることが大切です。
その他の諸条件・詳細については以下からご確認ください。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国土交通省)
補助金を活用するときのポイントと注意点
補助金は、使えると思っていたのに「申請できなかった」「期限を過ぎた」となるケースも少なくありません。制度を上手に活かすために、押さえておくべきポイントと注意点を解説します
制度に対応できる建築会社を選ぶ
補助金制度には、国や自治体に事前登録された「登録事業者」による施工が必須となるケースが多くあります。とくに「子育てグリーン住宅支援事業」や「ZEH補助金」などは、登録事業者以外で建てた住宅は対象外になるため注意が必要です。
補助金を活用したい場合は、締切から逆算して計画を立てましょう。いつまでに何を完了させる必要があるかを建築会社と明確に共有しておけば、手続きの遅れや漏れのリスクを減らせます。制度に詳しい担当者がいるかどうかも、安心して任せる業者選びで欠かせないチェックポイントです。
スケジュールは制度に合わせて逆算する
補助金制度には、交付申請の期限や着工・完了報告の提出期限が定められており、これらを守らなければ補助金は受け取れません。とくに注文住宅は、設計・契約・着工までに数か月を要するのが一般的なので、スケジュール管理がとても重要です。
活用したい制度がある場合は、締切から逆算し、いつまでに何を完了させる必要があるかを建築会社と共有しておくと、手続き漏れや遅れを防げます。補助金申請に慣れた事業者であれば、スケジュール調整や必要書類の準備もサポートしてもらえて安心です。
制度の併用可否を調べる
補助金制度には、併用できるものとできないものがあるため注意が必要です。国の事業についての併用可否は、以下のようになっています。
自治体独自の補助金制度については、原資が国の予算(国庫)である場合は、国の補助制度との併用が認められていないケースがほとんどです。
名称が異なっていても、補助金の出どころによって併用の可否が決まるため、公式サイトや直接の問い合わせで制度の詳細までよく確認することが大切です。
注文住宅の補助金でよくある質問(FAQ)
ここからは、注文住宅の補助金に関して寄せられることの多い疑問と、その回答をまとめて紹介します。
補助金は申請すれば必ずもらえる?
補助金には国や自治体の予算上限があるため、必ずもらえるとは限りません。また、要件を満たしていても審査結果によっては不採択となるケースもあります。とくに人気の高い制度では早期に受付が終了することもあるため、スケジュールに余裕を持って進めることが大切です。
着工済みの住宅には補助金は使えないの?
補助金は「契約前」または「着工前」が申請条件となっており、すでに工事が始まっている住宅は原則対象外となるケースがほとんどです。申請タイミングを間違えると、制度を利用できなくなるため、着工時期と申請スケジュールを建築会社と事前に確認しておきましょう。
補助金の申請は誰がするの?
補助金の申請手続きは、基本的に建築会社が代行してくれるのが一般的です。ただし、制度によってはその建築会社が制度に登録された「事業者」であることが条件とされています。制度の対象とするには、契約前に登録状況を必ず確認しておくと安心です。
補助金を申請するのに費用はかかる?
補助金の申請自体には費用はかかりませんが、手続きに必要な証明書類(登記簿謄本や住民票、性能証明書など)の発行にともない、数千円程度の実費が発生することがあります。費用が気になる方は、想定される実費を建築会社に確認しておくとよいでしょう。
土地がない状態でも補助金は申し込める?
補助金の正式な申請には、建築計画が確定していることが前提となるため、土地が未確保の状態では基本的に申請できません。対象物件や建築場所を確定してからでないと申請できないため、土地探しと同時並行で制度の確認を進めておくことをおすすめします。
まとめ
注文住宅では、補助金の活用有無によって、設備のグレードや月々の返済負担に大きな差が生まれます。国の制度だけでも最大160万円、自治体の補助金と併用すればそれ以上のコスト削減が可能になるケースも珍しくありません。
ただし、制度ごとに適用条件やスケジュールが異なるため、「気づいたときには対象外だった」とならないよう注意が必要です。不安がある場合は、補助金制度に詳しく、手続きまでサポートしてくれる住宅会社を選ぶことが重要です。
ポラスの「発見とちいえプラザ」では、では、補助金の要件確認から申請書類の準備・提出までをワンストップで支援しています。補助金を活かし、土地探しからの注文住宅を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
SUPERVISOR
監修者