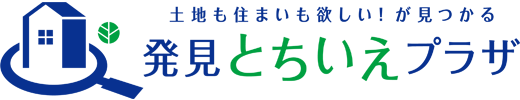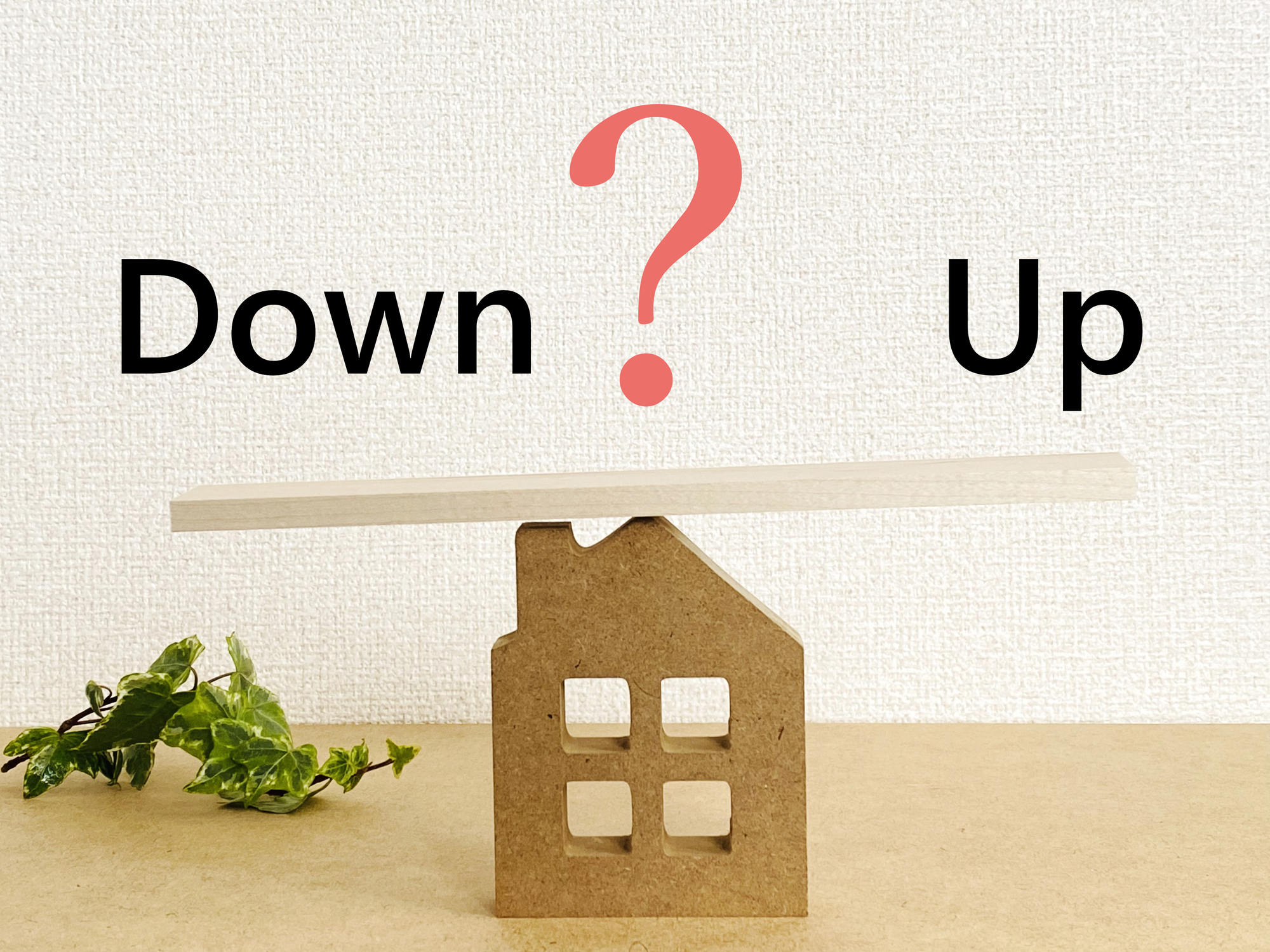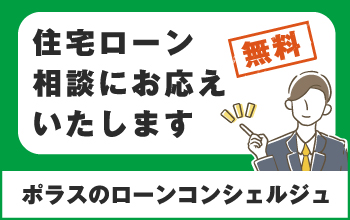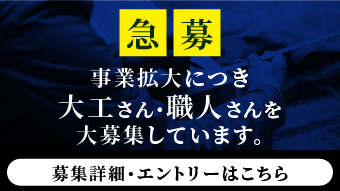平屋を建てる前に知っておこう!費用・土地・家づくりの基本

2025.7.28.
- 土地探し
その一方で、「平屋ってなんだか高そう」「うちの年収では無理かも」といった不安や先入観から、検討をためらう人も多いのが現実です。
この記事では、「平屋を建てるにはいくらかかるの?」「どんな広さの土地が必要?」「何から始めればいい?」といった基本を、初めて家づくりに取り組む方に向けてわかりやすく解説します。費用の内訳やローンの考え方、家づくりの流れまで、これからのマイホーム計画に役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。
平屋を建てる人は増えている
住宅市場において、平屋への注目度は確実に高まっています。国土交通省の「建築着工統計調」によると、2014年には新築住宅全体の約7.5%だった平屋の割合は、2024年には約16.8%と倍以上に伸びており、その人気の高さがうかがえます。
この平屋ブームの背景には、以下のようなメリットがあることが理由として考えられます。
ワンフロアで家事・移動がラク
平屋は階段の上り下りがないため、洗濯物を干したり、掃除機をかけたりといった日常の家事が、2階建てに比べると格段にスムーズです。小さなお子さんや高齢者がいるご家庭では、常に目が届く安心感も得られます。
構造がシンプルでメンテナンス性が高い
平屋はワンフロアのため、2階建てに比べて構造がシンプルです。そのため設計や施工の自由度が高まる傾向があります。また、高さを抑えられるので、外壁塗装や屋根塗装などのメンテナンス時に足場費用を抑えやすく、長期的な住宅維持費の面でも有利です。
上下移動がなく老後や子育て世帯にも適している
現在は元気でも、将来的に膝や腰に負担をかけたくないという方や、小さなお子さんの階段からの転落リスクを避けたいという方にも平屋は適しています。また、将来的にご両親との同居を検討している場合、階段がなくバリアフリーを実現しやすい平屋は理想的な住環境となるでしょう。
平屋を建てるのは2階建てより高いって本当?
平屋は2階建てに比べて坪単価が高くなりがちであるため、「平屋は高い」というイメージがあります。これは同じ延床面積の家を建てる場合、平屋の方が基礎と屋根の面積が広くなることが理由です。
坪単価とは、建物の延床面積1坪(約3.3㎡)あたりの建築費用のことです。 例えば、延床面積30坪の家を建てる場合、総2階建てなら1階15坪・2階15坪で基礎面積は15坪分で済みますが、平屋なら基礎面積は30坪分必要になります。屋根も同様で、平屋の方が面積が大きくなり、コストが上がる要因となります。
また、平屋を建てるには2階建てよりも広い土地が必要になることも、総費用が高くなる要因のひとつです。特に都市部では、土地代の影響は無視できません。
ただし、郊外の比較的土地価格が安いエリアを選んだり、間取りを効率化して建物面積をコンパクトにしたりすることで、予算内で理想の平屋を実現できる可能性は十分にあります。
平屋を建てるのに必要な費用とは?
ここからは、平屋を建てるために必要な費用の目安や内訳を見ていきましょう。
建物代だけじゃない!平屋を建てるのに必要な費用の内訳
平屋を建てる際には、建物本体の工事費以外にも様々な費用がかかります。全体像を把握して、資金計画を立てることが重要です。
|
項目 |
内訳 |
|
建物代(本体工事費) |
・基礎や土台、柱や梁(はり)などの構造部分 ・内外装の建材(壁、屋根、床など) ・設備費用(キッチン、ユニットバス、トイレ、照明など) ・上記にかかる工事費用 |
|
付帯工事費 |
・地盤改良費:地盤の強化が必要な場合に発生 ・外構費:塀や門扉、駐車スペース、庭の整備など ・水道引き込み工事費:上下水道の接続工事 ・電気・ガス配線工事費:電気やガスの引き込みにかかる費用 |
|
諸費用 |
・印紙税:契約書に貼付する印紙代 ・住宅ローンの借り入れ費用:保証料、事務手数料など ・不動産登記費用:登録免許税や司法書士報酬など ・火災保険料(+地震保険料):住宅ローンを仮入れる場合必須(地震保険は任意) |
一般的に、付帯工事費は建物代の20%、諸費用は10%が目安です。例えば本体工事費が3000万円の場合、付帯工事費は600万円、諸費用は300万円かかる計算です。本体にかかる消費税もあわせて見込んでおきましょう。
特に平屋の場合、広い敷地を活かした外構工事(庭やアプローチの整備)にこだわりたい方も多く、外構費が想定より高くなるケースも少なくありません。予算配分を考える際は、この点も考慮しておくことをおすすめします。
注文住宅の相場
土地を購入して注文住宅を建てる場合の費用相場を確認しておきましょう。
|
全国 |
首都圏 |
中京圏 |
近畿圏 |
その他の地域 |
|
|
建築資金(万円) |
3,406 |
3,402 |
3,415 |
3,491 |
3,384 |
|
延床面積(㎡) |
111.2 |
108.8 |
113.5 |
114.7 |
110.8 |
|
土地購入資金(万円) |
1,498 |
2,277 |
1,851 |
1,319 |
915 |
|
敷地面積(㎡) |
228.3 |
191.7 |
243.8 |
173.7 |
248.4 |
|
合計(万円) |
4,903 |
5,680 |
5,265 |
4,811 |
4,299 |
※住宅金融支援機構の「2023年度フラット35利用者調査」のデータをもとに編集部にて作成
首都圏では土地代が高いため建築資金が5,680万円と最も高く、その他の地域では4,299万円と比較的抑えられていることがわかります。平屋を建てる場合は、より広い敷地が必要になるため、地域による価格差の影響をより大きく受ける傾向があります。
また、この費用は平屋だけではなく、2階建てや3階建ても含んだ平均です。平屋に限ると、これより高くなる傾向がある点も、よく理解しておきましょう。
平屋を建てるときの予算・住宅ローンの考え方
続いて、平屋を建てるときの予算や住宅ローンについての考え方を解説します。
住宅ローンは年間の返済額を年収の20〜30%に抑えるのが無難
住宅ローンを組むときには、月々の返済額を年収の20〜30%以内におさめるのが無難とされています。安全を期すのであれば、25%以内に抑えることを検討しましょう。
例えば、世帯年収が600万円の場合、年間返済額は120万円〜150万円、月々の返済額は10万円〜12.5万円程度が目安となります。ここから計算すると、借り入れ可能額は3,787万円〜4,734万円になる計算です。※元利均等計算、返済期間35年間、変動金利0.6%で試算
なお、住宅ローンには「固定金利型」と「変動金利型」があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。特に近年は、将来的な金利上昇のリスクも指摘されているため、返済額の増加に備え、無理のない資金計画を立てることが重要です。住宅ローンは「借りられる金額」ではなく「返せる金額」を基準に、慎重に検討しましょう。
頭金の考え方
近年は住宅ローンの金利が低かったこともあり、フルローン(頭金なし)を利用する方が増加傾向にありました。リクルートの「2023年首都圏新築マンション契約者動向調査」によると、新築一戸建て購入者の27.5%がフルローンを利用しているとのデータもあります。
頭金があれば月々の返済額を抑えられますが、手元資金をすべて頭金に充てるのはリスクもあります。引っ越し費用や家具・家電の購入費、万が一の備えとして、ある程度の現金は手元に残しておくことも大切です。
土地購入から始める場合はつなぎ融資が必要になることも
土地を購入してから建物を建てる場合、住宅ローンは建物完成後でないと本格的な融資が実行されません。そのため、平屋を建てる土地購入から始める場合、土地代金の支払いのために一時的に借り入れる「つなぎ融資」が必要になるケースがあります。
つなぎ融資は住宅ローンよりも金利が高く設定されていることが多いため、利用する場合は費用面での検討も必要です。
土地購入からの家づくりについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
注文住宅の住宅ローンは土地代も借りられる?3つのパターンを徹底解説
平屋を建てるにはどのくらいの広さの土地が必要?
平屋は二階建てよりも広い土地が必要になりますが、具体的な目安はあるのでしょうか?
平屋に必要な土地の広さとは
家を建てるために最低限必要な土地の広さは、建ぺい率と容積率という法的な制限によって決まります。
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。一方、容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合を指します。なお、平屋の場合は建築面積と延床面積がほぼ同じとなるため、実質的には建ぺい率のみで考えるケースが多いです。
例えば建ぺい率50%の土地で30坪の平屋を建てるには、最低でも60坪の土地が必要になる計算です。
ただし、これはあくまで法的に「最低限」必要とされる広さです。土地の広さは庭やカーポート、アプローチなどのスペースも考慮して考えましょう。
平屋を建てる土地はどう探す?
平屋を建てるときには、「土地を先に買ってから建物を考えるべき?」「それとも建築会社を決めてから土地を探すべき?」と迷いがちです。
結論から言うと、土地と建物の依頼先探しは、同時進行で進めるのがベストです。その理由は以下の通りです。
土地の制約に合わせた最適な設計が可能
土地だけを先に購入してしまうと、その土地の形状や接道条件などによって、希望していた間取りの平屋が建てられない可能性があります。
その点、建築会社と一緒に土地を探せば、「この土地なら理想の平屋が建てられるか?」という視点で判断できるため、土地と設計のミスマッチを避けられるのがメリットです。
予算配分を最適化できる
土地に費用をかけすぎると、建物の予算が圧迫されてしまいかねません。予算内でで土地と建物のバランスを考えながら検討すれば、無理のない範囲で、満足度の高い家づくりが実現できます。
土地と建物を一括して相談できる会社なら手間も時間も省ける
土地探しと建物設計を同時進行するときに、それぞれ別の会社に依頼すると、情報共有や調整の手間がかかり、平屋づくり全体の進行が煩雑になりがちです。
その点、土地と建物の両方を一括で相談できる会社であれば、窓口を一本化できるため、打合せのスケジュール管理もスムーズに進められるのでおすすめです。
平屋の家づくりはどう進む?
平屋を建てる基本的な流れは以下のとおりです。
STEP 01:建物・建築場所のイメージづくり
家族のライフスタイルや将来の計画を話し合い、理想の平屋像を明確にします。「子どもがのびのび過ごせる家にしたい」「将来の親との同居も考えたい」といった要望を整理しておきましょう。
STEP 02:予算の検討
年収や貯蓄額をもとに、無理のない資金計画を立てます。土地代と建物代のバランスも考慮し、総予算を決定します。
STEP 03:建築会社探し
平屋の建築実績が豊富で、土地探しから対応してくれる会社を探します。複数の会社を比較検討し、信頼できるパートナーを見つけましょう
STEP 04:住宅ローン事前審査
希望する金融機関で住宅ローンの事前審査を受けます。借入可能額を把握することで、現実的な予算設定ができます。
STEP 05:土地探し
建築会社と一緒に、予算と希望条件に合う土地を探します。平屋に適した広さや形状、法的制限なども含めて検討します。
STEP 06:建物設計打合せ
土地が決まったら、その土地に最適な平屋の設計を進めます。間取りや仕様について、家族の要望を具体的に形にしていきます。
STEP 07:土地の買付・土地契約
気に入った土地が見つかったら、買付証明書を提出し、正式に土地売買契約を締結します。
STEP 08:建物の工事請負契約
建物の設計がまとまったら、建築会社と工事請負契約を締結します。
STEP 09:間取り・仕様詳細打合わせ
外壁や内装の色、設備機器の詳細など、細かな仕様を決定していきます。
STEP 10:建築確認申請
建築基準法に適合しているかをチェックするため、行政機関に建築確認申請を提出します。
STEP 11:住宅ローン本審査
建築確認が下りたら、住宅ローンの本審査を申し込みます。
STEP 12:土地決済(所有権移転)
住宅ローンの承認が得られたら、土地代金を支払い、所有権を移転します。
STEP 13:着工
いよいよ建築工事が始まります。近隣への挨拶も忘れずに行いましょう。
STEP 14:建物完成
竣工検査を経て、夢の平屋が完成します。
重要なのは、理想の暮らしやマイホーム像をイメージし、それを建築会社と共有しながら進めることです。また、年収や貯金をもとに早めに資金計画を立てることも、住宅会社・土地選びをスムーズに進め、予算オーバーを防ぐためには重要です。
なお、この流れは一般的な目安で、実際には土地の状況や建築会社によって多少前後することがあります。期間としては、全体で8〜12ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。
まとめ
平屋は2階建てより坪単価が高くなる傾向がありますが、立地選びや設計の工夫次第で、予算内で理想の住まいを実現することは十分可能です。
理想の平屋を成功させるポイントは、早めの資金計画と信頼できる建築会社選びです。平屋建築の実績が豊富で、土地探しから設計・施工までトータルでサポートしてくれる会社であれば、土地と建物の予算バランスを見たうえで、敷地条件に合わせた最適なプランを提案してもらえるのでおすすめです。
私たち発見とちいえプラザでも、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた平屋づくりを土地探しからワンストップでお手伝いしています。「平屋を建てたいけれど、何から始めればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
SUPERVISOR
監修者