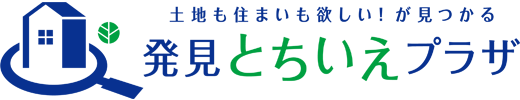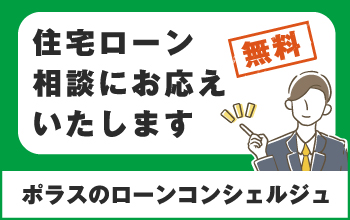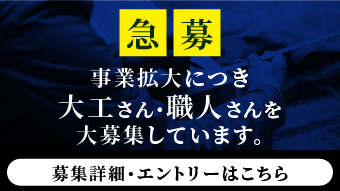注文住宅の完成までの期間は?目安と工程別スケジュール【徹底解説】

2025.4.26.
- 注文住宅
注文住宅を建てたいと考えたとき、気になるのが「完成までの期間」ではないでしょうか。とくに初めての注文住宅では、工程や期間のイメージがつかめず、不安を抱える方も多いでしょう。
この記事では、注文住宅の完成までにかかる一般的な期間の目安を、計画から引き渡しまでの流れにあわせて解説します。期間が延びやすい原因や、スムーズに進めるためにできることなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
注文住宅完成までの期間は?全体スケジュールをまず把握しよう
注文住宅の完成までにかかる期間は、平均して10〜14カ月程度といわれています。土地探しからはじめる場合は、さらに時間を要することが多く、2年近くかかるケースも少なくありません。一方で、条件が整っている場合には、7〜8カ月ほどで完成に至ることもあります。
この期間の違いは、土地の有無や条件の整理状況、プラン決定のスピードによるものです。「注文住宅=時間がかかる」という前提を持ち、スケジュールを逆算しながら進めていくことが、満足度の高い家づくりへの近道となるでしょう。
工程別に見る注文住宅のスケジュールと目安期間
注文住宅が完成するまでには、いくつかの段階を踏んで進行していきます。ここでは、各工程の内容と一般的な期間の目安を、順番に見ていきましょう。
計画スタート〜情報収集・資金検討(1〜3カ月)
家づくりの第一歩として、家族の希望条件や予算感をすり合わせる期間です。この段階で、希望エリアや理想の間取り、必要な部屋数、ライフスタイルに合った設備など、住まいに求める条件を整理しておくことで、この後のステップが大幅に進めやすくなります。
同時に、展示場見学や住宅会社のカタログ請求、住宅ローンのシミュレーションなどをおこない、情報の土台を整えていくことをおすすめします。住宅会社の候補をリストアップする段階でもあるため、信頼できそうな企業の特徴を比較し、初期リサーチを進めておくとよいでしょう。
土地探し・住宅会社選び(3〜6カ月)
土地探しと住宅会社選びは、家づくり全体を左右する重要なステップです。土地は、希望に合う物件がすぐに見つからず、長期化することもあります。駅からの距離や学区、日当たりなど譲れない条件を整理し、候補を絞っていきましょう。
住宅会社は、施工実績や対応エリア、打ち合わせの進め方などを比較するのがポイントです。土地と建物をまとめてサポートできる会社であれば、工程を並行して進めやすくなり、全体の期間短縮にもつながります。
条件に合う土地が見つかったら、売買契約を結び、次の工程に進みます。
プラン設計・詳細打ち合わせ・契約(2〜6カ月)
理想の住まいを形にするための設計プランと仕様の打ち合わせには、想像以上に時間がかかることがあります。間取りの細部や設備仕様、収納の配置など、検討すべき項目は多岐にわたるため、家族内で事前に優先順位を整理しておくと、打ち合わせが効率よく進みます。
また、この段階では住宅ローンの申請も並行して進めるのが一般的です。金融機関の審査には一定の時間がかかるため、早めに必要書類を整え、余裕をもって手続きを始めましょう。
設計内容の最終確認が済んだら、建築工事請負契約を締結します。
着工〜建築工事(3〜6カ月)
契約が完了すると、いよいよ建築工事が始まります。まずは地盤調査をおこない、必要に応じて地盤改良を実施。その後、基礎工事、上棟、屋根や外壁、内装工事へと順に進んでいきます。季節や天候によって、工期が1〜2週間程度前後するケースもあります。とくに梅雨や冬季は要注意です。
また、施工会社の体制によっても進行の安定性は変わります。地域特性を熟知し、職人や協力会社との連携が強い体制を持つ会社であれば、天候リスクを想定したスケジュール調整が可能で、工程の乱れを最小限に抑えやすくなるので安心です。
完成・引き渡し・入居準備(約1カ月)
建物の工事が完了したあとは、いくつかの最終手続きを経て引き渡しへと進みます。
まずは、施工会社による完成検査や第三者機関による検査を実施し、問題がなければ登記手続きや施主確認へ移ります。このタイミングで、住宅ローンの金銭消費貸借契約(いわゆる「金消契約」)や融資の実行もおこなわれます。
また、入居前には引越しの段取りや行政手続き、電気・ガス・水道の開通準備なども必要です。滞りなく新生活を始めるために、引き渡しの1カ月前から計画的に準備を進めておくと安心です。
注文住宅を建てる具体的な流れについては、以下の記事で詳しく説明しています。
注文住宅の契約・購入の流れは?進め方を全14ステップで徹底解説
注文住宅の期間が延びやすい原因と注意点
理想の家を建てるまでには、多くの工程と調整が必要です。ここからは、注文住宅のスケジュールが遅れやすい主な原因と、その対策について見ていきましょう。
土地が見つからない・契約がまとまらない
希望条件に合う土地がなかなか出てこない、比較検討に時間がかかるといったケースは珍しくありません。また、購入希望が固まったあとでも、契約条件の見直しや確認ミスなどによって交渉が長引くこともあります。
家づくりの起点となる土地探しが難航すると、その後のスケジュール全体に大きく影響します。こうした遅れを防ぐには、プロの不動産会社や住宅会社の助言を早い段階で受けることが効果的です。スピード感を持って意思決定を進めるためにも、事前準備と段取りは入念にしておきましょう。
プラン打ち合わせが長引く
間取りや仕様の打ち合わせは、家づくりの要ともいえる重要な工程ですが、時間がかかりやすいポイントです。
家族内で希望がまとまらず、何度も修正を繰り返したり、担当者との認識のズレが原因で議論が平行線になることもあります。また、「ここはこだわりたい」という思いが強すぎることで検討が長引き、工程全体の遅れにつながるケースも多く見られます。
スムーズに進めるためには、あらかじめ希望条件に優先順位をつけておくことが効果的です。納得のいく家づくりに時間をかける価値はありますが、同時に「完成目標日」を意識しながら進める姿勢も大切です。
住宅ローンの審査や融資実行が遅れる
住宅ローンに関する手続きも、家づくりの工程全体に影響を及ぼすことがあります。
事前審査の準備が不十分だったり、本審査で書類不備があった場合、スケジュールが大きく後ろ倒しになってしまいます。つなぎ融資や分割融資の仕組みをよく理解していないと、必要な手続きが遅れ、着工や引き渡しのタイミングに影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
また、金融機関ごとに審査スピードや書類の必要内容が異なるため、複数機関を比較しながら、早めに相談・書類準備を進めることがリスク回避につながります。
天候や資材納期のトラブル
注文住宅の工期は、天候や資材供給の状況によっても大きく左右されます。
たとえば、梅雨や台風、冬場の冷え込みなどが、基礎工事や外装工事の進行に影響を及ぼすことは珍しくありません。また、社会情勢や地域要因によっては、建材や設備機器の納品が遅れ、工事が中断してしまうこともあります。
さらに、職人不足や繁忙期の混雑によって、予定どおりに作業が進まないケースも見られます。こうしたトラブルを最小限に抑えるには、着工時期を見極めることと、段取りに強い住宅会社を選ぶことが重要です。
書類・申請関係の遅れや確認漏れ
建築確認申請や開発許可などの行政手続きは、家づくりのスケジュールに直接影響する要素の一つです。提出書類に不備があると、再提出や確認作業に時間を取られ、工程全体が後ろ倒しになる可能性があります。住民票や印鑑証明、登記書類など、本人が用意すべき書類も遅れず手配が必要です。
また、こうした手続きは慣れていないと見落としが起こりやすく、申請のタイミングや対応の順番を誤ることで遅延のリスクが高まります。不安がある場合は、申請業務までしっかりフォローしてくれる住宅会社を選ぶと安心です。
注文住宅の完成までの期間を短縮するためにできること
注文住宅は自由度が高い分、どうしても時間がかかりがちです。ここでは、施主側の工夫によってスケジュールを効率よく進めるための具体的な方法をご紹介します。
ゴールから逆算してスケジュールを立てる
「来年の春には新居で暮らしたい」など、完成時期の目標をあらかじめ決めておくと、スケジュールにメリハリがつきやすくなります。そこから逆算することで、各工程に必要な期間や着手すべきタイミングが明確になり、「今なにをすべきか」の優先順位もはっきりするためです。
とくに注文住宅では、「気づいたら1カ月過ぎていた」といった停滞がスケジュール全体に影響することもあるため、家づくり全体を「プロジェクト」として捉え、工程ごとに締切意識を持つことが大切です。
家族の希望を事前に整理し、優先順位を決めておく
注文住宅の打ち合わせでは、家族の理想や要望が多岐にわたるため、話がまとまらず時間がかかってしまうことがあります。無理なく進めるためには、あらかじめ「絶対に外せない(must)」と「あったら嬉しい(want)」を区別し、優先順位を明確にしておくことが効果的です。
この整理ができていると、打ち合わせ中の判断がぶれにくくなり、修正も最小限に抑えることができます。さらに、予算配分や仕様決定の場面でも選択がしやすくなるため、結果的に工程全体の短縮にもつながります。
土地と建物はセットで考える
理想の住まいをスムーズに実現するためには、「どんな家を、どこに建てたいか」をセットで考えるのがおすすめです。土地が決まってから家づくりを始めると、設計のやり直しや二度手間が発生しやすく、スケジュールが長引く原因になる傾向があるためです。
土地と建物を一体で検討することで、条件に合う土地を見つけやすくなり、建物設計とのすり合わせも早い段階で進めることができます。土地探しから設計・施工・引き渡しまでをワンストップで対応できる会社を選べば、スケジュール調整の手間も軽減され、完成までの時間短縮が叶うでしょう。
地盤・施工に強い「地域密着型企業」を選ぶ
注文住宅のスケジュールを安定して進めるには、地元の気候や法規制、地盤特性に精通した企業を選ぶことも大切です。たとえば、地域特有の季節要因に応じた施工時期の判断や、自治体ごとの申請手続きの流れなどに慣れている会社であれば、ムダな待機期間や調整ロスを防ぎやすくなります。
また、地場のネットワークを活かした土地情報や施工パートナーとの連携も、提案力や工事精度に直結します。こうした「地域対応力」が高い会社を選べば、工期のブレを抑える安心感を得られるのでおすすめです。
家族での役割分担を決めておく
家づくりをスムーズに進めるには、家族全員で協力し合う姿勢が欠かせません。とくに注文住宅では検討事項が多く、夫婦で話し合うべきテーマが頻繁に発生します。あらかじめ「誰が何を担当するか」を分担しておくと、迷いや重複が減り、意思決定がスピーディになります。
たとえば、契約関連は事務手続きが得意な人が担当し、間取りやインテリアはそれらにより関心の高い人が進めるといった分担も有効です。さらにLINEや共有カレンダーなどで進捗を「見える化」しておくと、家族全体の動きが整理され、時間短縮にもつながります。
担当者との相性を見極め信頼関係を築く
注文住宅は長期間にわたるプロジェクトになるため、「この人になら何でも相談できる」と思える担当者と出会えるかどうかが、家づくり全体の満足度に大きく影響します。相性のよい担当者は、意思疎通がスムーズで、判断に迷ったときの助言や提案力にも期待できます。
とくに、土地の購入から引き渡しまでを一貫して担当してくれる体制が整っていれば、情報共有のムダが減り、スケジュールの遅延リスクも抑えやすくなり安心です。見積もり段階のやり取りのなかで、相性や対応力をしっかり見極めましょう。
注文住宅が完成するまでの期間でよくある質問
ここでは、注文住宅の完成までの期間について、よくある質問とその回答を紹介します。
二世帯住宅や複雑な間取りだと長引く?
二世帯住宅や変則的な間取りの家は、一般的な住宅に比べて打ち合わせの回数が多くなりがちなのは事実です。世帯間の意見調整が必要な場合もあり、間取り決定までに時間がかかる傾向があることが理由です。また、法的な制約や確認申請の内容が複雑になることも多く、申請・審査の工程が長引く原因になることもあります。
さらに、施工そのものも規模や難易度が上がるため、工期が通常より1〜2カ月程度長くなるケースも珍しくありません。計画時点でスケジュールにゆとりを持たせておくことをおすすめします。
冬に建てると工期は長くなる?
冬季の建築は、季節特有の気象条件により工期が延びる可能性があります。それは、気温が低いとコンクリートの乾燥・強度確保に通常より時間がかかることがあり、「養生期間」が長く設定されることがあるためです。また、日照時間がとくに短くなる地方や、降雪が多い地域では、作業時間そのものの確保が難しくなることもあるでしょう。
ただし、施工体制がしっかり整っている会社であれば、天候リスクを見越した工程管理や資材の先手手配により、影響を最小限に抑えることが可能です。工期の見通しやリスク対策については、着工前にあらかじめ確認しておくと不安を軽減できます。
ローン審査が通らないと着工できない?
注文住宅の着工には、住宅ローンの本審査を通過し、正式な契約を結ぶことが前提となります。本審査が通らない状態では、金融機関からの融資が確約されないため、着工には進めません。
そのため、事前審査はできるだけ早い段階で申し込み、必要書類の準備も計画的に進めておくことが大切です。金融機関によっては混雑状況や確認内容によって、審査に2〜4週間以上かかる場合もあるため、スケジュールに余裕を持たせておきましょう。
まとめ
注文住宅を建てるには、平均して約10〜14カ月ほどの期間が必要です。だからこそ、計画の段階で「いつまでに完成させたいのか」を明確にし、各工程の流れと必要な時間をあらかじめ把握しておくことが重要です。
ポラスの「発見とちいえプラザ」では、土地探しから設計・施工・引き渡しまでを一貫してサポートしています。工程間のズレを最小限に抑え、理想の家づくりを安心して進めることができるので、注文住宅のスケジュール管理に不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
SUPERVISOR
監修者