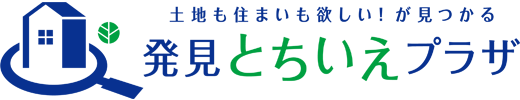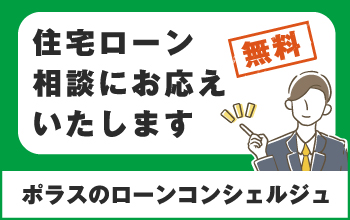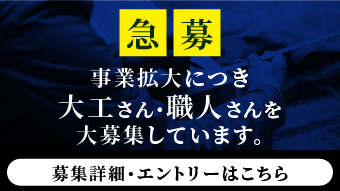注文住宅の諸費用は実際いくら?内訳と相場を完全解説
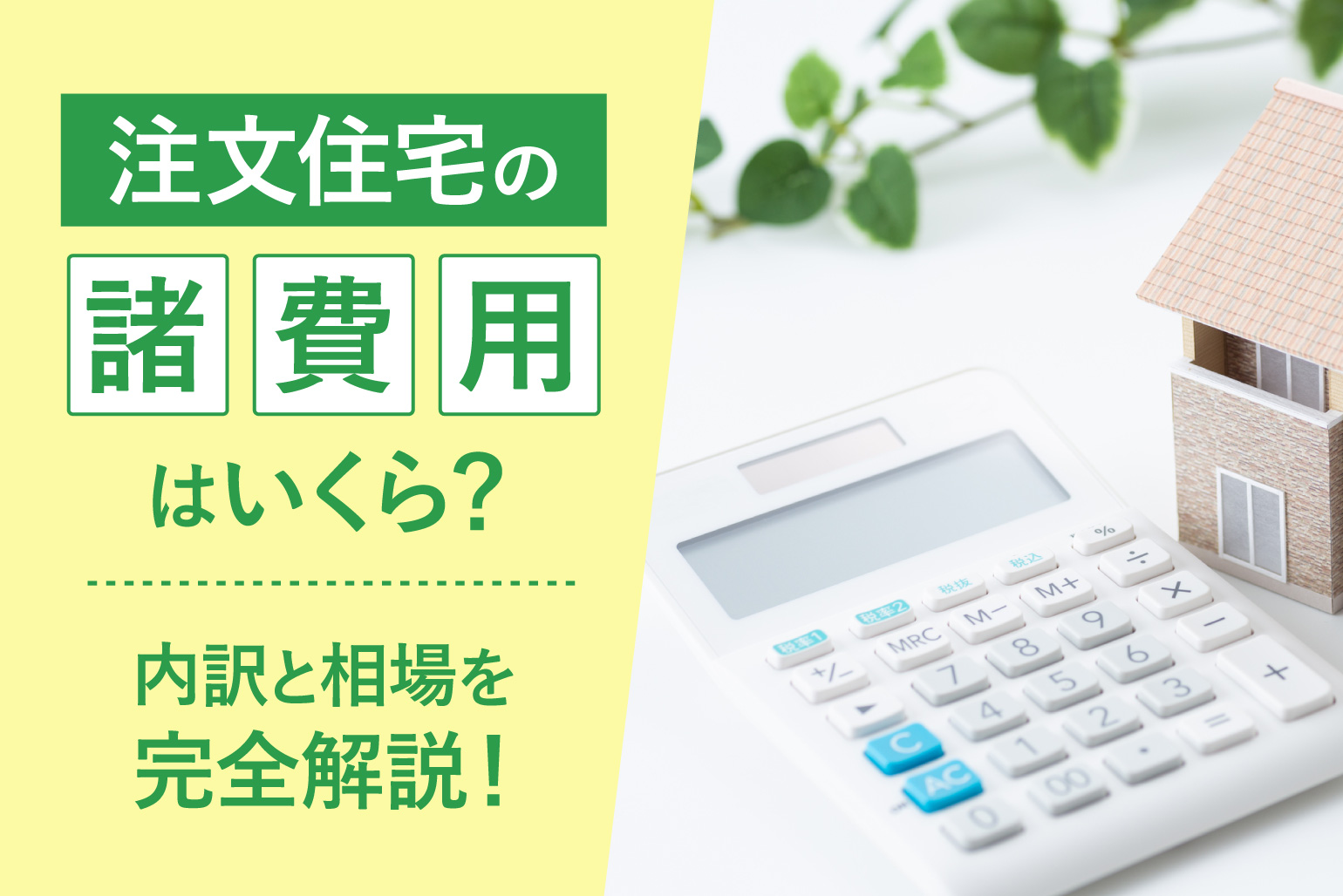
2025.4.26.
- 注文住宅
この記事では、注文住宅にかかる諸費用の内訳を詳しく解説します。費用を抑える方法や注意点も紹介しますので、資金計画で後悔しないためにも、ぜひ参考にしてください。
注文住宅の「諸費用」とは?
注文住宅の「諸費用」とは、土地購入や建築工事、住宅ローンの契約時などに発生する、建物本体・付帯工事費以外の各種費用をまとめた総称です。一般的に建物にかかる費用の合計額に対して、約10%程度が諸費用の目安とされており、たとえば総額3,500万円の注文住宅なら約175万円ほどになります。
諸費用は登記費用や各種税金、ローン関連手数料など、かかるタイミングや種類もさまざまで、地域や建築会社によって金額差が出ることも少なくありません。建物価格だけに注目していると「こんなにかかるの?」と驚くケースもあるため、諸費用をあらかじめ把握しておくことが、予算オーバーを防ぐ第一歩です。
注文住宅の土地購入にかかる諸費用
仲介手数料
土地を不動産会社の仲介で購入する場合には、仲介手数料がかかる場合があります。これは売主が個人の場合に不動産会社への報酬として支払う費用で、売主が法人の場合は発生しません。
仲介手数料は法律で上限が定められており、「物件価格の3%+ 6万円+消費税」で求めます。たとえば2,000万円の土地であれば、仲介手数料は72万6,000円(税込)となります。
登記費用(所有権移転登記)
土地を購入した際には、「所有権移転登記」という法的な手続きが必要となり、これにかかる費用が登記費用です。
登録免許税は土地価格の0.2%が標準ですが、令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合は軽減措置が適用され、0.15%となります。
また、登記手続きを専門家に依頼する場合は司法書士報酬が必要になり、5〜7万円程度が相場です。
参考:No.7191 登録免許税の税額表
印紙税
土地を購入する際は、売買契約書に「印紙税」が課税されます。税額は、契約書の金額に応じて以下のように決まっています。
<印紙税の例>※令和9年3月31日までの軽減措置適用後の金額
● 1000万円以下:5千円
● 1000万円超〜5000万円以下:1万円
● 5000万円超〜1億円以下:3万円
印紙は郵便局などで事前に購入しておくのが一般的なので、あらかじめ用意しておきましょう。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
不動産取得税(土地)
土地を購入したあとには、「不動産取得税」という地方税が課税されます。購入から3〜4カ月後に、自治体から納税通知書が届く仕組みです。
税額は原則、土地の評価額×4%ですが、住宅用地の場合は軽減措置が適用され、評価額×1/2×3%で計算されます(令和9年3月31日まで)。評価額は実際の売買価格とは異なるため、あらかじめどの程度になるかを確認しておくと安心です。
注文住宅の建築時にかかる諸費用
建築確認の申請費
家を建てるには、建築基準法に適合していることを確認するための「建築確認申請」が必要になります。その手続きにかかる費用が「建築確認申請費」で、10万〜20万円程度が標準的な費用です。
費用は建築規模や構造、申請先の自治体・民間検査機関によっても異なります。申請は建築会社が代行するケースがほとんどなので見積もりに含まれているのが一般的ですが、念のため確認しておきましょう。
印紙税
建物の建築請負契約書にも、土地と同様「印紙税」が課税されます。税額は契約金額に応じて、以下のように段階的に設定されています。
<印紙税の例>※令和9年3月31日までの軽減措置適用後の金額
● 1000万円以下:5千円
● 1000万円超〜5000万円以下:1万円
● 5000万円超〜1億円以下:3万円
水道加入金(水道分担金)
水道加入金とは、新築住宅で水道を使用する際に支払う費用のことです。これは水道施設の整備にかかる費用の一部を建築主が負担するもので、水道局への「加入申請」と同時に納付します。
金額は自治体によって大きく異なり、たとえば一般的な20mm口径の場合、埼玉市では11万円である一方、千葉市では29.7万円となっています。水道加入金は、水道管の口径や新設・引き込み状況によっても変動するため、具体的な金額は事前に確認しておくと安心です。
設計監理料
設計監理料とは、建築士が建物の設計図面を作成し、工事中も図面通りに施工されているかをチェックする業務(監理)に対して発生する費用です。
ハウスメーカーの規格住宅ではあらかじめ含まれていることが多いですが、自由設計や建築家との家づくりでは別途請求されるケースもあります。
費用の目安は、建築費の3〜5%前後、もしくは数十万円程度です。依頼内容や建築会社の体制によって変動するため、契約前に見積書に含まれているかよくチェックが必要です。
登録免許税(建物表題登記)
新築住宅を建てた際には、建物の所有権を法的に登録する「建物表題登記」と「保存登記」が必要になります。このうち、登録免許税が発生するのは「保存登記」であり、建物の固定資産税評価額に対して0.15%が課税されます(軽減措置適用時)。
また、登記手続きは専門性が高いため、司法書士に依頼するのが一般的です。その際にかかる司法書士報酬は、5〜7万円程度が相場になります。
参考:No.7191 登録免許税の税額表
地鎮祭・上棟式など儀式費用
地鎮祭や上棟式といった儀式は、注文住宅を建てる際に行われることの多い慣習です。必須ではなく任意ですが、地域や世代によっては「やっておくのが普通」とされることもあります。
地鎮祭では神主への謝礼や供物などで3〜5万円程度、上棟式では職人への手土産やご祝儀に、あわせて10万円程度が目安です。ただし最近では、儀式を省略するケースも増えており、地域性や建築会社の方針によっても異なります。不安があれば、担当者に相談して判断するのが無難です。
不動産取得税(建物)
新築住宅を建てた際には、建物にも「不動産取得税」が課税されます。土地と同様に、取得から数カ月後に自治体から納税通知書が届くのが一般的です。
税額は建物の固定資産税評価額×4%が原則ですが、令和9年3月31日までは3%の軽減税率が適用されます。
さらに、新築住宅には1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)の控除もあり、これにより実質的な負担が大きく減る場合があります。控除が適用されるには諸条件があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
参考:不動産取得税に係る特例措置
住宅ローン契約時にかかる諸費用
ローン手数料
住宅ローンを申し込む際には、金融機関への「融資事務手数料」が発生します。これはローンを実行するための手続きにかかる費用で、金融機関ごとに金額や算出方法が異なります。
大きく分けて「定率型」と「定額型」があり、定率型では借入額の2.2%程度が目安となります。一方、定額型では3〜5万円程度の手数料が設定されるケースが多いようです。手数料の方式は金融機関によって異なるため、金利以外の諸条件もあわせて確認しておくことが大切です。
ローン保証料
ローン保証料とは、万が一返済ができなくなった際に、金融機関が保証会社に肩代わりしてもらうための費用です。借入額や返済期間によって異なりますが、相場は借入額の0〜2%程度とされており、たとえば3,000万円を借り入れる場合は30〜60万円前後になることもあります。
支払い方法には、契約時に一括で支払う「外枠方式」と、金利に上乗せして支払う「内枠方式」があり、どちらを選べるかは金融機関によって異なります。最近は保証料ゼロを掲げる金融機関もあるため、よく比較検討して選びましょう。
団体信用生命保険(団信)
団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンの契約者が返済期間中に万が一死亡または高度障害になった場合、残りのローンが保険で完済される制度です。住宅ローンを組む際は原則加入とする金融機関がほとんどで、金利に団信の保険料が含まれている「金利込み型」となっているのが一般的です。
保険内容は金融機関によって異なり、ガンや三大疾病の保障が付くタイプは金利が年0.2〜0.3%程度上乗せされることもあります。保障内容と金利のバランスを見ながら選ぶことが大切です。
火災保険料
住宅ローンを利用する際には、火災保険への加入も必須となるのが一般的です。火災はもちろん、風災・盗難・水災などのリスクに備えるもので、5年〜10年分を一括で支払うのが主流です。
保険料は建物の構造や補償内容によって異なりますが、10〜20万円前後が相場です。なお、火災保険とセットで地震保険に加入することも多く、こちらも補償内容に応じて費用が加算されます。補償の範囲と保険料のバランスを見ながら、必要なプランを検討しましょう。
印紙税
住宅ローンの契約書にも印紙税が課税されます。正式には「金銭消費貸借契約書」と呼ばれ、契約書の金額に応じて印紙を貼付する必要があります。
課税額は建物契約と同様で、たとえば1,000万円超〜5,000万円以下なら1万円、5,000万円超〜1億円以下なら3万円が必要です(令和9年3月31日までの軽減措置適用後の金額)。
参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
登録免許税(抵当権設定登記)
住宅ローンを借り入れる際、金融機関は担保として建物や土地に「抵当権」を設定します。この手続きにかかる費用が「登録免許税」で、借入額の0.4%が原則ですが、令和9年3月31日までは軽減措置により0.1%に引き下げられています。
抵当権設定登記も司法書士に依頼するのが一般的で、報酬は5〜7万円程度が相場です。登記費用は契約時の諸費用のなかでも金額が大きくなりやすいため、早めに見積もっておくと安心です。
参考:No.7191 登録免許税の税額表
注文住宅の諸費用を抑えるためにできること
諸費用は工夫次第で削減できる項目もあります。ここでは、施主側で検討できる「諸費用を抑えるための具体策」を紹介します。
仲介手数料が不要な土地を選ぶ
土地購入時にかかる仲介手数料は、土地代に比例するため数十万円規模になることも多く、費用を抑えるうえで見直したいポイントです。
具体的には、不動産会社が売主となっている「自社物件」や、建築会社が保有している分譲地であれば仲介手数料が不要となる点は見落とせません。たとえば2,000万円の土地なら、仲介手数料だけで約72万円(税込)かかりますが、自社物件ならこの費用が不要になります。
ただし、手数料を抑えることにこだわりすぎて、条件のよい土地を逃してしまうのは本末転倒です。費用と土地条件のバランスを見ながら、総合的に判断するようにしてください。
不要と思う儀式は省略する
地鎮祭や上棟式といった儀式は、建築前後に行われる伝統的な行事ですが、法的な義務はなく、費用面から見ても任意です。最近では合理性を重視し、これらの儀式を省略するケースも増えており、施主の判断で行わない選択も可能です。
ただし地域性もあるため、費用を抑えたい場合は「儀式をやるべきか」を事前に施工会社に相談してみることをおすすめします。
金利だけでローンを決めない
住宅ローンを選ぶ際、多くの人が「金利の低さ」ばかりに注目しがちですが、それだけで判断するとかえって総支払額が高くなるケースもあります。たとえば、保証料や事務手数料、団体信用生命保険(団信)の内容などを見落とすと、初期費用で数十万円の差が出ることも少なくありません。
また、建築会社が提携する金融機関を選ぶと、手数料の優遇や手続きの簡略化といったメリットがある場合もあります。ローンを比較する際は、「金利+諸費用+付帯条件」を含めた総コストで検討することが大切です。
注文住宅の諸費用についてのよくある質問
Q. 諸費用はローンに組み込める?
諸費用の一部は、住宅ローンに組み込んで借りることも可能です。ただし、対応の可否や対象となる費用項目は金融機関ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
たとえば 【フラット35】では、印紙代、融資事務手数料、抵当権設定費用、火災保険料などが対象に含まれるケースがあります。また、ローン特約の有無や審査条件にも関係するため、自己資金とのバランスも考えながら検討することをおすすめします。
Q. 諸費用が足りないときはどうすればいい?
もし諸費用が想定よりも不足した場合、まずは契約内容やオプションの見直しで費用を調整できないか検討してみましょう。たとえば、外構工事や設備の一部を入居後に回すといった選択も有効です。
また、親からの資金援助を受ける場合には「住宅取得等資金の贈与税非課税制度」が活用できる可能性があります。この制度の要件を満たすと、最大1,000万円までの贈与が非課税となるため、大きな資金援助を受けやすくなるのがメリットです。
なお、最終的には、自己資金の再配分や借入額の増額も視野に入れながら、住宅会社と相談して進めることが大切です。土地と住宅を一括で相談できるワンストップ体制なら、全体の予算配分も調整しやすくなるのでおすすめです。
参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
まとめ
注文住宅では、建物本体の価格に加えて、さまざまな諸費用がかかります。とくに契約時や着工時に現金で支払う必要のある項目も多いため、ローンに頼るだけではカバーしきれない「先払い費用」の存在を理解しておくことが大切です。
ポラスの「発見とちいえプラザ」では、土地探しから設計・施工・資金相談までをワンストップで支援しています。明朗な見積りと、千葉・埼玉エリアに精通した専門スタッフによる丁寧なサポートで、諸費用まで含めた安心の家づくりを実現いたします。
「建物価格だけで考えていたら想定外の出費が…」とならないためにも、ぜひ一度ご相談ください。
SUPERVISOR
監修者
.jpg)
岩井 学 (いわい まなぶ)
宅地建物取引士