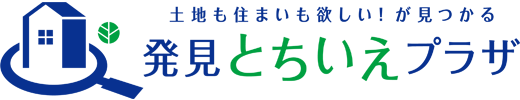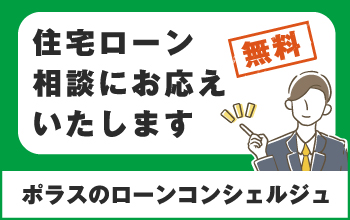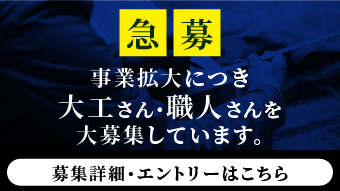注文住宅とは?種類・費用・メリット・デメリットを徹底解説!

2025.3.7.
- 注文住宅
この記事では、注文住宅の基本や種類、費用相場、建築プロセス、さらに成功させるためのポイントなどを詳しく解説します。理想の家づくりを実現するために、ぜひ参考にしてみてください。
注文住宅とは?建売・分譲住宅との違いも解説
まずは、注文住宅の特徴や、建売・分譲住宅との違いについて詳しく解説します。
注文住宅とは?自由度の高い家づくりができる住宅
注文住宅とは、土地を購入してから、あるいはすでに持っている土地に、自分が選んだハウスメーカーや工務店などで建てる家のことです。まだ家ができあがっていないので、間取りやデザイン、設備などを自由に決められるのが特徴です。
自分の希望や好み、ライフスタイルを間取りや仕様に反映できるため、こだわりのある人に向いています。
注文住宅と建売・分譲住宅の違い
家を購入するときには、注文住宅のほか、建売住宅や分譲住宅という選択肢もあります。それぞれの違いも確認しておきましょう。
建売住宅との違い
建売住宅は、すでに建築済みの家を土地とあわせて購入することが特徴です。すでに家が完成している、あるいはプランが決まっているので、間取りや仕様を自由に選ぶことはできません。
そのため家に大きなこだわりがない人や家づくりに時間をかけたくない人、できあがったものを見て選びたい人などに向いています。
分譲住宅との違い
分譲住宅は、ハウスメーカーや工務店などが所有する分譲地に建てられた、あるいはこれから建てられる家を指します。建売住宅と同様に、間取りや仕様を自由に選ぶことはできません。
なお、小規模な分譲住宅は建売住宅と呼ばれることもあり、明確な区分はありませんが、大規模な分譲地だと統一された街並みが形成されるのが特徴です。
注文住宅の種類と特徴
注文住宅には「自由設計型」と「規格型」の2種類があります。こだわりの強さや、予算・スケジュールを考慮しながら、どちらが自分にあっているか検討しましょう。
自由設計型注文住宅とは?完全オーダーメイドの住まい
自由設計型は、法律の範囲内で、ゼロから自由に設計できる住宅です。間取りやデザイン、設備の選択肢が幅広く、外壁の素材からドアの取っ手に至るまで、すべて自由に決められます。
そのため、自分の理想の家がありとことんこだわりたい人や、狭小地・変形地など規格型に対応できない土地に家を建てたい人に向いています。
規格型注文住宅とは?コストを抑えた効率的な住宅
規格型注文住宅とは、複数のプランのなかから好みのものを選んで建てる住宅のことです。基本的な設計や構造は決まっているものの、間取りはあらかじめ用意されたプラン集のなかから選べ、設備の仕様もある程度自由に選べることがほとんどです。
自由設計型と比較すると自由度は劣るものの、その分低コストで家を建てられ、建築期間も短縮できます。規格型注文住宅は、ゼロから考えるのは負担が大きいと思う人、ある程度決まったなかから選びたい人に向いています。
注文住宅のメリットとは?
建売住宅・分譲住宅ではなく、注文住宅を選ぶメリットを紹介します。
間取りやデザインの自由度が高く個性を出しやすい
注文住宅は、すでに建築済みの建売住宅・分譲住宅と異なり、間取りやデザインを自由に決められるのが特徴です。家族のライフスタイルにあわせて設計できるため、好みや理想を反映しやすく、個性を出しやすい点がメリットといえます。
たとえば、広々としたリビングを2階に設ける、吹抜けやアイランドキッチンを採用するなど、理想の住まいを実現しやすいのが魅力です。
自分で土地を選べる
土地とのセット購入になる建売住宅・分譲住宅は、家はもちろん土地も自分では選べません。その結果、土地と建物に自分の生活スタイルを合わせていかざるを得ない場合もあります。
一方、注文住宅であれば、場所や広さ、形状など、自分の希望にあった土地を選べます。たとえば、家庭菜園を楽しめる広い庭を持てる土地や、静かな住宅地など、暮らしに合わせた選択が可能です。
予算の調整が可能
注文住宅は、こだわる部分とコストを抑える部分のメリハリをつけやすいのもメリットです。
たとえば、長い時間を過ごすリビング、あるいは頻繁に使う水回りにはコストをかけ、寝室はシンプルにする。設備はハイグレードにする代わりに、壁紙やフローリングは標準的なものにするなど、予算内で優先順位をつけながら計画し、理想とコストのバランスを取れるのが魅力です。
建築過程を確認でき、安心して家づくりができる
建売住宅・分譲住宅ですでに建築が済んでいる場合は、建築過程が見えません。そのため、「手抜き工事なのでは?」という不安を抱くこともあります。
しかし、注文住宅であれば、基礎工事から仕上げまでの工程を自分の目で確かめながら進められるので、品質への信頼感が高まります。また、建築を担当する大工さんや職人さんの顔が見えることも安心材料のひとつです。
好きなハウスメーカーに依頼できる
注文住宅は、自由にハウスメーカーや工務店を選べるのもメリットです。建売住宅や分譲住宅ではすでに施工会社が決まっていますが、注文住宅であれば、自分のこだわりにあった会社を選べます。
ハウスメーカーによって得意とする建築スタイルや工法、設備しようが異なるため、事前に比較・検討すれば、より理想の家に近づくことができるでしょう。
建築条件付き土地の場合は選べない点に注意
注文住宅であっても、建築条件付き土地に建てる場合は、建築会社が決まっている点に注意です。建築条件付き土地とは、特定のハウスメーカーや工務店で建築することを前提に販売されている土地を指し、施工会社は自由に選べません。
建築条件付き土地について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
建築条件付き土地とは?やめたほうがいい?メリット・デメリットやトラブルを防ぐポイントなどを徹底解説
注文住宅のデメリットとは?
注文住宅は自由度が高く理想の住まいを実現しやすい一方で、デメリットもあります。ここでは、具体的にどのような点に注意すべきかを解説していきます。
契約から入居までに時間がかかる
すでに建築済みの建売住宅・分譲住宅であれば、売買契約が済めば最短1ヶ月〜2ヶ月前後で入居できます。しかし、注文住宅の場合は、購入を決めてから設計や施工を進めるため、入居までは1年程度かかるのが一般的です。
さらに土地探しから始めるときや、デザイン・設備などにこだわりがある場合は、1年半かかるケースも珍しくありません。そのため入居のタイミングを考慮し、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
建売住宅と比較してコストが高くなる傾向がある
自分の好みを自由に反映できる注文住宅は、こだわればこだわるほどコストが高くなる傾向があります。とくにハイグレードな設備や仕様を選んだ場合、予算を大幅に超えることも。
ただし、すべての注文住宅が高額になるわけではありません。できるだけシンプルにしたり、設備のグレードを抑えたりするなど工夫することで、かえって低コストに抑えられる場合もあります。予算オーバーしないためには、どこにお金をかけるのか、優先順位を考えながら進めましょう。
完成するまで実物を確認できない
すでに建築済みの建売住宅・分譲住宅であれば、購入前に実際の家の雰囲気や2階の窓からの眺め、設備の使い勝手や動線などを確認できます。しかし、注文住宅は目の前に現物がないので、完成するまで実際どのような家になるのかわからず、思い描いていたものと仕上がりが異なる可能性があります。
ただし、近年は3DやVR(バーチャルリアリティー)などを活用し、できあがった家を具体的にイメージできるよう、ハウスメーカーや建築会社もさまざまな工夫をしています。こうした技術を活用すれば、理想と現実のギャップを埋めやすくなるでしょう。
打ち合わせや決定事項が多く、時間と手間がかかる
注文住宅は、家の間取りから使用する建材、設備などを一つひとつ打ち合わせできめていくので、時間と手間がかかります。とくに、こだわりが強いほど選択肢が増え、決定に時間がかかりやすくなる点は理解が必要です。
ただし、この過程こそが注文住宅ならではの醍醐味といえ、楽しめるポイントでもあります。負担を軽くしたい場合は、こだわりが少ない部分はハウスメーカーや建築会社に任せたり、規格型注文住宅を選んだりするのがおすすめです。
注文住宅の費用と相場を知ろう
注文住宅を建てる際には、建物の工事費だけでなく、土地の整備や各種手続きにかかる費用も考慮が必要です。ここでは、注文住宅の主な費用内訳や、相場を解説します。
注文住宅の費用内訳とは?
注文住宅の費用は、大きく「本体工事費用」「付帯工事費用」「諸費用」の3つに分かれます。
本体工事費用
本体工事費用とは、土地の条件や注文内容などを加味しない、建物そのものの価格のことです。主に基礎工事や柱や梁(はり)などの構造部、内外装の建材、キッチンやユニットバスなどの設備、およびそれらの工事費用が含まれます。
一般的に、ハウスメーカーや工務店ごとに標準仕様が決められており、それに沿って価格の目安が示されます。ただし、会社によって含まれる内容が異なるため、見積もりを比較する際は「どこまでが本体工事に含まれているのか」を確認することが重要です。
付帯工事費用
付帯工事費とは、建物を建てるために必要な周辺工事やインフラ整備の費用で、具体的には以下のようなものが含まれます。
⚫︎地盤改良費(地盤が弱い場合に補強するための工事費)
⚫︎外構費(塀や門扉、駐車場の整備など)
⚫︎水道の引き込み工事費
これらの費用は、土地の状況や建築条件によって大きく変わりますが、建物代の20%程度を見込んでおくのが一般的です。
諸費用(税金・ローン手数料など)
注文住宅の購入には、工事費用だけでなく、各種手続きにかかる以下のような費用も必要です。
⚫︎印紙税(契約書に貼る印紙代)
⚫︎住宅ローン手数料(融資を受ける際に必要な手数料)
⚫︎不動産登記費用(保存登記や抵当権設定登記にかかる費用)
⚫︎仲介手数料(土地を不動産会社を通じて購入する場合の手数料)
⚫︎火災保険料・地震保険料(住宅ローンを組む場合は必須とされることが多い)
諸費用は、建物工事費の10%程度を見込んでおくと安心です。
注文住宅の価格相場はどれくらい?
注文住宅を検討するときに、もっとも気になるのが費用です。ここでは、注文住宅の価格相場を詳しく解説します。
【土地あり】注文住宅の費用相場
すでに土地を所有している場合の注文住宅の建築資金は以下のとおりです。
延床面積は、首都圏の主な都県もほぼ全国平均と同じ水準で、大きな差はないことがわかります。都市部でも住宅の規模は大きく変わらず、コストの差は主に施工費や資材費の違いにあると考えられます。
【土地なし】注文住宅の費用相場
土地を所有していない場合の住宅建築資金総額は以下のとおりです。
建物価格は地域によって大きな差はありません。一方、トータル費用は、土地購入資金が加わるため、土地代が高いエリアほど費用が高額になっています。
また、土地ありのケースと比べて、土地に費用を回すために、建物の延床面積を小さくしたり、全体的にかける費用を抑えたりしていることもわかります。
予算別の注文住宅の事例
注文住宅の坪単価(1坪あたりの建築費)の平均は、土地なしの場合、首都圏で約106万円です。これをもとに、予算別にどのような注文住宅が建てられるかを紹介します。
1,000万円台で建てる家の特徴
1000万円台で建てられるのは、20坪以下のコンパクトな注文住宅です。15〜18坪だと、階段やホールのスペースを考慮すると2階建ては難しく、平屋が現実的な選択肢となります。間取りの目安としては、4.5畳×1〜2間と12〜14畳のLDKといったシンプルな構成が一般的です。
この価格帯では、自由設計型の注文住宅は難しく、基本的には規格型注文住宅になるでしょう。
2,000万円台で建てる家の特徴
2000万円台になると、20坪台の注文住宅を建てることが可能になります。とくに2,000万円台後半になれば、6畳×2〜3間と14〜16畳のLDKを確保できます。
2,000万円台前半の予算なら、規格型注文住宅を選ぶことで、同程度の広さの家を建てられる可能性があるので検討しましょう。
3,000万円台で建てる家の特徴
3,000万円台になると、30坪台の注文住宅が建てられるようになります。これは、新築注文住宅の平均坪数である35坪〜36坪に近く、平均的な広さです。
間取りとしては、6畳×3〜4間+16〜20畳のLDKが標準的で、30坪後半になれば、土間収納やウォークインクローゼットなど、プラスαのスペースも確保できます。
この価格帯では自由設計型の注文住宅も選択肢に入るため、理想の住まいをより具体的に実現しやすくなるでしょう。
4,000万円台で建てる家の特徴
4,000万円台では、40坪以上の自由設計型の注文住宅が可能になります。間取りの例としては、家族の人数やライフスタイルに応じて、6〜8畳×3〜4部屋、または8〜10畳×2〜3部屋に、18〜22畳のLDKを配置する形が考えられます。部屋数を少なめにして、土間収納やウォークインクローゼット(WIC)を充実させるのもおすすめです。
また、30坪台にとどめてハイグレードな設備や高性能な断熱・耐震仕様を取り入れることもできるため、住み心地やデザイン性にこだわった家づくりをしたい方に向いている価格帯といえます。
注文住宅を建てる流れとスケジュール「建築プロセスを知ろう」
ここでは、注文住宅を建てる流れを順番に紹介します。
STEP1. 住まいのイメージを考える
まずは、理想の住まいや希望のエリアを家族で話し合い、イメージを固めましょう。予算を気にせず希望をリストアップし、Must(絶対ほしい)とWant(あれば嬉しい)に分類します。優先順位をつけることで、取捨選択がスムーズに進みます。
STEP2. 予算を検討する
注文住宅にかけられる全体予算を決め、住宅ローンの借入額をシミュレーションしましょう。年収の20~30%以内に収まる、無理のない返済計画を立てることが重要です。土地と建物の予算は、建築会社と相談しながら配分を調整するのをおすすめします。資金援助の可能性を親に確認し、不安があればFPにも相談してみましょう。
STEP3. 土地探し・購入
建築会社探しと並行して、土地探しも進めます。土地の予算を抑えることで、建物にコストをかけられるようになります。理想の土地が見つかったら購入を申し込み、手付金を支払って売買契約を結びましょう。
STEP4. 建築会社・ハウスメーカー選び
全体予算が決まったら建築会社探しを開始します。ハウスメーカーと工務店の特徴や得意分野を理解し、比較検討しましょう。住宅展示場やモデルハウスを見学し、担当者と直接話すことで、信頼できる会社を見極めます。
STEP5. プランニング・見積もりの検討
建築会社と打ち合わせをおこない、希望に沿った建物設計を進めます。土地の形状に合わせた間取りを考え、生活動線や収納も重視しましょう。見積もりを依頼し、コストバランスを調整しながらプランを確定することが重要です。
STEP6. 契約
設計内容と見積もりに納得したら、工事請負契約を結びます。契約を締結後、間取りや内装、外装、設備などについて、細かい打ち合わせを進めていきます。契約内容をよく確認し、工期や支払い条件も明確にしておきましょう。
STEP7. 着工
工事が始まる前に、地鎮祭をおこなうかどうかを検討します。現場の様子や工事の進捗は定期的にチェックし、職人さんたちと積極的にコミュニケーションを取ると、マイホームが完成するまでの過程を存分に楽しめます。
STEP8. 上棟
家の骨組みが完成し、屋根が組まれる「棟上げ」は、建築の節目となり完成までの過程を実感できる機会です。家族や関係者と祝うイベントとして棟上げ式をおこなうかを検討しましょう。
STEP9. 竣工・引き渡し
建物が完成したら、完了審査と施主検査を実施し、不備があれば補修を依頼します。補修が完了し、問題が解消されたことを確認したうえで引き渡しを受けることが重要です。鍵を受け取ったら、新居での生活がいよいよ始まります。
注文住宅を建てる流れについて詳しくは以下の記事をご覧ください。
注文住宅の契約・購入の流れは?進め方を全14ステップで徹底解説
注文住宅で後悔しないためのポイント
注文住宅は自由度が高い反面、事前の準備や計画が不十分だと後悔につながることも。理想の住まいを実現するために、押さえておきたいポイントを紹介します。
実現したい希望を具体的に書き出す
まずは、実現したいテーマ(例:開放感のあるリビング、収納重視、子どもが遊びやすい家など)を明確にしましょう。家族のライフスタイルに合った要望を具体的にリストアップすることで、必要なスペースや間取りが見えてきます。
たとえば、共働き夫婦なら家事効率を重視し、在宅ワークが多い場合は書斎スペースを確保するなど、今の暮らしを基準に考えることが大切です。また、現在の住まいで不満に感じている点を洗い出し、新居で解決する方法を考えていくのもおすすめです。
イメージに近い写真や間取りを準備しておく
雑誌やSNSなどで気になるデザインや間取りをピックアップし、具体的なイメージをつくっておくと、家づくりの方向性が明確になります。具体的なイメージをハウスメーカーや工務店と共有できると、ズレが生じにくくなるのもメリットです。
モデルハウスの見学なども活用し、実際のサイズ感や生活動線を確認するのもよいでしょう。
予算をしっかり決めて無理のない計画を立てる
予算を考えるときには、住宅ローンのシミュレーションをおこない、返済負担率は年収の20~30%に抑えることが重要です。建物価格以外に必要な付帯工事費や諸費用なども考慮し、余裕のある資金計画を立てましょう。
家はあくまで暮らしの基盤であり、建てたあとの生活が苦しくなっては本末転倒です。親からの資金援助や補助金制度の活用なども検討しながら、無理のない予算設計を心掛けることが重要です。
土地と建物は同じ会社に依頼する
注文住宅の失敗を防ぐもっとも確実な方法は、土地探しと家の設計を同じ会社に依頼することです。自分ではいいと思った土地であっても、実際には希望の広さの家を建てられなかったり、地盤改良などに高額な費用がかかることがあります。
また、土地と建物を別々に決めると、建物の設計で妥協せざるを得なくなるかもしれません。土地はそこに建てる建物をイメージして探すことがポイントなので、家の設計を依頼する会社と一緒に、資金計画を考えたうえで探すことが重要です。
住みやすさを考慮した間取りを意識する
家族構成やライフスタイルの変化に対応できる、可変性のある間取りを考えることも大切です。たとえば、子どもの成長や老後を見据え、部屋をフレキシブルに使える設計にすると、長く快適に暮らせます。
動線にも配慮し、キッチンや洗面所、リビングなどの配置を工夫することで、より生活しやすい家になります。また、日当たりや風通し、収納スペースの確保にも配慮しましょう。そのためには、できるだけ多くの希望や情報をハウスメーカーや工務店と共有し、具体的なプランを練ることが大切です。
注文住宅の後悔1位は間取り|失敗しない対策を業界29年のプロが解説
注文住宅に関するQ&A
ここでは、注文住宅についてよくある質問とその回答を紹介します。
注文住宅の間取りをシミュレーションする方法は?
間取りをシミュレーションしたいときには、インターネットのシミュレーションツールを活用する、建築会社やハウスメーカーが提供する間取りプランを参考にするなどの方法があります。
ただし、もっとも確実なのは、プロの建築士や設計士に相談し、具体的な要望を伝えてプランを考えてもらうことです。プロは多くの事例を見てきており、動線や日当たりなど、長く快適に暮らせる間取りを提案してくれます。プロの視点でアドバイスを受けるほうが、より満足度の高い間取りに仕上がりやすくなるでしょう。
注文住宅と分譲住宅、どちらがコスパが良い?
注文住宅は間取りやデザインの自由度が高く、希望に合わせた家を建てられるのが魅力ですが、その分コストがかかる傾向があります。一方、分譲住宅は規格化された設計でコストを抑えられ、比較的安価に購入できます。
ただし、コストパフォーマンスを考えるのであれば、家の寿命まで考慮することが重要です。購入価格を抑えられても、使用されている材料によっては頻繁なメンテナンスが必要になり、結果的に費用がかさむこともあります。長期的なメンテナンス費用や、快適に暮らせる期間も考慮したうえで比較検討してみてください。
注文住宅のローン審査は厳しい?
住宅ローンの審査では、年収や借入額、物件の担保価値が重視されます。さらに注文住宅の場合、住宅ローンの実行前に一時的に資金を借りる『つなぎ融資』や、複数回に分けて融資を受ける『分割融資』が必要になることも。
ハウスメーカーや工務店が提携している金融機関の住宅ローンは、比較的審査が通りやすく、条件が優遇されることもあるため、検討してみるとよいでしょう。
注文住宅の住宅ローンについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
注文住宅の住宅ローンは土地代も借りられる?3つのパターンを徹底解説
注文住宅で「理想の家」を叶えよう!
注文住宅を検討するときには、自由設計型・規格型の違いを理解し、自分に合ったスタイルを選ぶことが大切です。建売・分譲住宅との違いやメリット・デメリットも比較して、後悔のない家づくりを目指しましょう。また、予算や建築の流れを把握し、計画的に進めることで、スムーズに理想の住まいを実現できます。
ポラスの「発見とちいえプラザ」なら、土地と建物を1人の担当者にまとめて相談できるため、安心して家づくりを進められます。「理想の家を建てられない土地を購入してしまった」「土地に費用をかけすぎて家の予算がショートした」といった失敗を防ぎやすくなるので、ぜひ活用してみてください。
SUPERVISOR
監修者
.jpg)
岩井 学 (いわい まなぶ)
宅地建物取引士