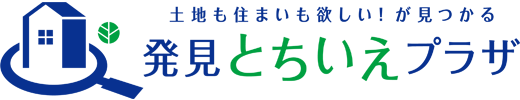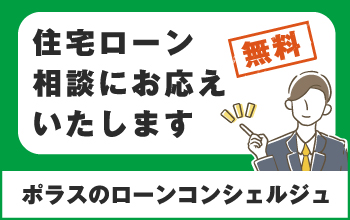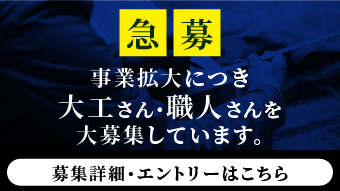3階建ての家のメリット・デメリットとは?後悔しないための工夫も紹介

2025.7.28.
- 注文住宅
都市部での家づくりには、「何かを諦めること」が前提になりがちです。限られた予算の中で、広さを取るか立地を取るか。多くの方がこの選択に悩まれることでしょう。
そんなとき、限られた土地でも空間を確保できる「3階建ての家」は、広さと利便性の両立を叶える有力な解決策となり得ます。近年、都心部を中心に3階建て住宅への注目が高まっているのも、このような背景があるからです。
この記事では、住宅のプロとして数多くの3階建て住宅を手がけてきた経験をもとに、3階建てを選ぶメリット・デメリットや、後悔しない家にするためにできる工夫などを詳しく解説します。3階建ての家を検討中の方はぜひ参考にしてください。
3階建ての家にするメリットは?
まずは、3階建て住宅が持つ魅力的なメリットから見ていきましょう。
床面積を効率的に確保できる
3階建て住宅最大のメリットは、狭い敷地でも希望の延床面積を確保しやすいことです。
例えば、建ぺい率60%の20坪の敷地に家を建てる場合、1階の建築面積は12坪が上限となります。2階建てなら延床面積は24坪程度ですが、3階建てなら36坪の住まいを実現できる可能性があります※。この12坪の違いは、子ども部屋1室分、書斎、収納スペースなど、暮らしの質を大きく左右する空間となるでしょう。
特に都市部では、「もう少し広ければ」という要望を叶えてくれる現実的な選択肢といえます。
※実際に建てられる広さは、容積率やその他の規制の影響を受けます。建ぺい率・容積率について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
建ぺい率60%・容積率200%の土地で建てられるのはどんな家?
地価の高い地域でもマイホームを持てる
3階建ての家は平屋や2階建てと比べて敷地面積が小さくて済むため、都心・駅近など土地価格が高い場所でも予算内に収まる可能性が高まります。これは「延床で取り返す」という考え方で、立地の利便性を諦めずに、理想の住まいを実現する手法です。
実際に、駅徒歩5分圏内で40坪の土地を探すと予算オーバーでも、25坪程度なら手が届くケースは少なくありません。浮いた土地代を建物にかけることで、快適性も両立できるのです。
採光・通風・眺望の良好な環境が得やすい
3階や屋上部分は、周囲の建物の影響を受けにくいため、良好な日当たりや風通し、眺望を確保しやすくなります。
特に住宅密集地では、1・2階は隣家に囲まれていても、3階なら開放的な環境を得られることが多いものです。ルーフバルコニーや3階リビングなどを選択すれば、「空に近い暮らし」の心地よさを実感しやすくなるでしょう。また、吹き抜けを設けることで、この上階の明るさを下階にも取り込むことが可能です。
多様な空間設計を実現できる
3階建てはフロアにゆとりがあるため、用途別に立体的なゾーニングがしやすくなります。例えば、1階をガレージと玄関、2階をLDKと水回り、3階を寝室と子ども部屋といった、2階建てでは難しい空間設計も可能になります。このような構成にすると、車を持つ家庭でも、敷地を有効活用しながら快適な住まいを実現できる点がメリットです。
また、ルーフバルコニーや書斎、アトリエなど、2階建てでは確保が難しい「プラスα」の空間を設けることで、ライフスタイルに合わせた多彩な空間づくりができるのも魅力です。
二世帯住宅など分離型設計にも対応しやすい
階ごとのゾーニングがしやすい3階建ては、親世帯・子世帯の生活空間を適度に分離した二世帯住宅にも適しています。
たとえば、1階を親世帯、2階を共用のLDK、3階を子世帯のプライベートスペースとすれば、適度な距離感を保ちつつ、必要な時には支え合える理想的な二世帯住宅が実現できます。
それぞれのスペースを2階を挟んで分けることで騒音や生活リズムの違いによるストレスも軽減しやすく、3階建てだからこそできる独立性の高い二世帯住宅が叶うでしょう。
水害などのリスクにも強い設計ができる
近年、豪雨による浸水被害が各地で発生するなかでは、「万一の備え」を重視した家づくりが求められます。3階建ての家であれば、生活の中心をを2階以上に計画することで、想定外の浸水リスクを大幅に軽減できるのは利点です。
ハザードマップで浸水リスクが高い区域を避けることが大前提ですが、万一の事態に備え、垂直方向への避難が可能な3階建ては、防災面でも有効な選択となるでしょう。
固定資産税の軽減措置が適用される可能性がある
新築住宅に対しては、一定の要件を満たせば固定資産税が減額される措置が取られています。減額期間については、一般的な住宅は3年間ですが、耐火・準耐火構造の3階建て住宅なら5年間に延長され、長期優良住宅の認定を受ければ最大7年間の軽減措置を受けられる可能性があります。
こうした住宅は建築コストが高くなる傾向がありますが、長期的に見れば税制面でのメリットを受けられるうえ、安心して暮らせる住まいになることもメリットです。
3階建ての家にするデメリットは?
メリットが多い3階建て住宅ですが、デメリットもあります。事前に把握し、対策を講じることが重要です。
階段移動が多く、家事・育児時の動線が大変になる
階建て最大のデメリットは、日常的な上下移動の負担です。
洗濯物を3階のバルコニーに干しに行く、1階の駐車場と3階を小さな子どもを抱えて行き来する——こうした動作が毎日続くことになります。特に育児中や高齢期には、この負担は決して軽視できません。
実際に3階建てにお住まいの方からは、「若いうちは平気だったが、年を重ねるにつれて階段がつらくなってきた」「3階は使わなくなった」という声もよく聞かれます。
温度差・空調ムラが課題になりやすい
3階建ては上下の温度差が生じやすく、冷暖房効率が悪化しがちです。
暖かい空気は上に、冷たい空気は下に下がる性質があるため、夏場は3階が非常に暑くなる一方で、冬場は1階が冷え込みやすくなります。特に吹き抜けや階段室があると、空調効率が下がる傾向があります。
全館空調を導入しない場合、各階にエアコンを設置する必要があり、光熱費がかさむ可能性もあるでしょう。
地震や風圧の影響を受けやすい
建物は重心が低いほど安定するため、高さのある3階建ての家は地震や強風による影響を受けやすくなります。
特に建築面積が狭く縦に細長い3階建てで、周囲に同じような高さの建物が少ない場合は風圧を直接受けやすくなり、台風時の揺れや音が気になるという声も聞かれます。
1階の日当たり確保が困難な場合もある
3階建てを検討するのは住宅密集地が多く、隣家が接近している場合、1階の日照が遮られる可能性があります。
南側に3階建ての建物があると、1階の居室はほぼ一日中薄暗い状態になることも。1階に寝室や子ども部屋を配置する場合は、採光計画を十分に検討することが大切です。
メンテナンスの費用が高額になりがち
外壁塗装や屋根工事の際、3階建ては足場の設置費用が平屋や2階建てより割高になりがちです。高さが増すことで安全対策も厳しくなり、工事期間も長くなる傾向があります。
築10年、20年と経過した際のメンテナンスコストは、事前に想定しておくべき重要な要素です。
3階建てで後悔しない!快適な家にするためにできる工夫
デメリットを理解した上で、それらを軽減し、快適な3階建て住宅を実現するための具体的な工夫をご紹介します。
動線設計とゾーニングで階段の負担を減らす
階段移動の負担を最小限にするには、生活動線を意識したゾーニングが重要です。
最も効果的なのは、LDKと水回り(キッチン、洗面、浴室)を2階に集約する設計です。家族がよく使う空間を中心階にまとめることで、日常の移動を大幅に削減できます。また、洗濯機置き場とバルコニーを同じ階に配置すれば、洗濯動線もスムーズです。
予算に余裕がある場合は、エレベーター設置スペースを確保した設計も、将来的な対策として有効です。
断熱・換気・空調制御で快適な室内環境を整える
温度差の問題は、家自体の断熱性能・気密性能の向上と空気循環の工夫で大幅に改善できます。
吹き抜けや階段室にはシーリングファンを設置し、空気の循環を促進させましょう。窓はガラスが2枚・3枚になった複層ガラスを採用し、外気温の影響を最小限に抑えることも大切です。
理想的なのは全館空調システムの導入です。初期費用は高くなりますが、各階の温度を均一に保ち、快適性と省エネ性を両立できます。床暖房との併用も効果的で、足元から温まることで体感温度が向上し、設定温度を下げても快適に過ごせます。
耐震・耐風性能を確保した構造設計をおこなう
3階建ては建物の高さや重心のバランスにより、2階建てよりも地震や風の影響を受けやすいため、構造設計がより重要になります。
壁量の確保はもちろん、耐力壁のバランス配置、基礎設計の最適化が不可欠です。許容応力度計算による詳細な構造検討をおこない、それに適した仕様を選定する必要があります。
3階建ての設計・施工に豊富な経験を持つ会社に依頼すると、、安全性とコストのバランスを適切に保った設計が可能になるのでおすすめです。
採光設計や吹き抜けで1階の明るさを確保する
1階の採光不足は、設計の工夫で改善できます。
たとえば、ハイサイドライト(高窓)を活用すれば、隣家の影響を受けにくい高い位置から光を取り込みやすくなります。。中庭やライトコートを設けることでも、プライバシーを保ちながら1階にも十分な自然光をもたらすことが可能です。
階段部分に吹き抜けにし、上階の明るさを1階まで導く設計も効果的です。この場合、吹き抜け階段が廊下代わりにもなり、空間効率も向上します。
将来の修繕を見据えて外装材を選ぶ
メンテナンスコストを抑えるには、外装材選びが重要です。
初期コストは高くても、メンテナンス頻度の少ない素材を選ぶことで、長期的にはコストを削減できます。例えば、窯業系サイディングでも高耐候性塗料を使用したものや、金属系の外壁材などは、塗り替え頻度を減らすことにつながります。
屋根材も、ガルバリウム鋼板や高耐久瓦など、メンテナンス性に優れた素材を検討するとよいでしょう。
3階建ての家を検討するときの土地探しのポイント
3階建て住宅を成功させるには、土地選びの段階から注意すべきポイントがあります。
土地にかかる規制を把握し理解する
すべての土地には建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)・容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)が定められており、これが建築可能な規模を決定します。しかし、3階建ての場合は、これらに加えて各種斜線制限や高度地区、日影規制なども重要な制約となります。
例えば、北側斜線制限により3階部分が大幅にカットされ、想定していた間取りが実現できないケースは少なくありません。また、第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限があり、10mの規制がかかる場合は3階建てそのものが困難になる可能性もあります。
希望する3階建てが本当に建築可能かどうかは、土地購入前に専門家に確認することが重要です。
土地と建物は同じ会社に依頼すると安心
土地探しと建物設計を別々の会社に依頼すると、建築制限の見落としやプランの不一致が発生しやすくなります。
土地探しの段階から建築会社に相談することで、「この土地なら希望の3階建てが建築可能」「この予算なら、このエリアでこの規模の家ができる」といった総合的な判断が可能になります。その結果、土地契約後に建築制限が判明し、計画変更を余儀なくされるリスクを回避できるのは大きなメリットです。
また、地盤調査の結果を踏まえた基礎設計や、敷地の形状を最大限活用した設計提案も期待できます。土地と建物の予算配分をあらかじめ調整することで、「土地にお金をかけすぎて、理想の家が建てられなくなった」という失敗も防ぎやすくなるでしょう。
まとめ
3階建て住宅は、限られた敷地で広さと立地を両立できる魅力的な選択肢です。階段移動の負担、温度差の問題、構造的な課題などのデメリットはあるものの、これらは適切な設計と工夫により軽減することが可能です。
最も重要なのは、土地探しの段階から、3階建て住宅の設計・施工に豊富な経験を持つ専門会社に相談することです。土地探しから建築の専門家が関わることで、法的制限を事前に把握し、敷地を最大限活用した理想の住まいを実現できるでしょう。
私たち発見とちいえプラザでも、土地探しから3階建ての設計・施工まで、理想の住まいづくりをワンストップでサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
SUPERVISOR
監修者