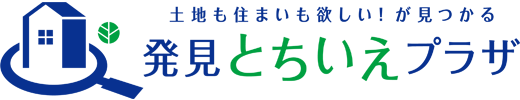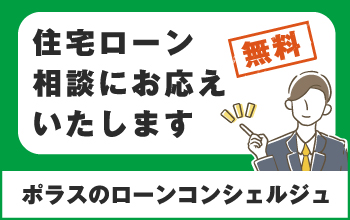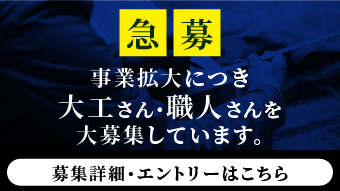注文住宅の頭金はいくら必要?相場と判断ポイントを解説

2025.5.27.
- 注文住宅
最適な頭金の額は、家族の収入や貯蓄状況、将来のライフプランによって一人ひとり異なります。「平均的な頭金額」よりも「自分たちにとって無理のない計画」を重視することが大切です。
この記事では、頭金の平均相場や比較シミュレーション、少ない・多い場合のリスクとメリット、さらに借入額を抑える制度や工夫まで幅広く紹介します。それぞれの家庭にあった適切な判断ができるよう、参考にしてみてください。
注文住宅の頭金とは?
注文住宅の「頭金」とは、物件価格のうち、住宅ローンではなく自分で現金で支払う自己資金のことです。
かつては「頭金は2割が基本」といわれていましたが、これは住宅ローンの上限を物件価格の80%に制限する金融機関が多かったためとされています。近年ではこの制限が緩和され、マイホーム取得を後押しする制度も整ってきたことから、頭金に対する考え方も変わってきました。
頭金を入れることで借入額が減ると、月々の返済負担や利息の総額を抑えられるという利点がありますが、多ければよいとは限りません。将来の生活資金とのバランスを見ながら、無理のない金額設定が重要です。
注文住宅の頭金はいくらが相場?
実際にどの程度の頭金を用意しているのかは、多くの方が気になるポイントです。リクルートの2024年首都圏新築マンション契約者動向調査によると、2024年の新築一戸建て契約者の自己資金比率(頭金の割合)は以下のようになっています。
参考:2024年首都圏新築マンション契約者動向調査|リクルート
新築一戸建て購入者の頭金(自己資金比率)は平均13.7%という結果です。また自己資金ゼロ、つまり頭金ゼロのフルローンを選ぶ人は30.2%にのぼり、さらに5%未満を合わせると半数を超える56.0%が、頭金をほとんど入れずにマイホームを取得しています。
頭金を抑えて注文住宅を建てるケースが増え、資金計画は多様化しているといえるでしょう。
注文住宅の頭金による返済額・総返済額の違いを比較
それでは実際に、頭金の割合によって住宅ローンの返済額がどれほど変わるのかを比較してみましょう。以下は、5,000万円の物件を頭金0%〜20%で借り入れた場合の試算です。
たとえば、頭金を10%入れたケースでは、0%に比べて月々の返済額が約1.3万円軽くなり、総返済額でも約536万円の差が生じます。このように、頭金の有無が返済総額に大きく影響することがわかります。
ただし、無理に多く入れることで生活資金が圧迫されては本末転倒です。全体の資金バランスを見極めながら判断することが大切です。
注文住宅の頭金が少ない場合のメリット・デメリット
注文住宅の頭金は多い方が安心とされがちですが、少額に抑えることにも利点があります。ここからは、頭金を少なくした場合に考えられるメリットとデメリットの両面を見ていきましょう。
メリット
まずはメリットから紹介します。
手元に資金を残せる
頭金を少なくすることで、手元にまとまった資金を残すことができます。これにより、引っ越し費用や家具・家電の購入、子どもの教育費や将来のライフイベントに備えることができ、新生活を安心してスタートしやすくなります。予期せぬ支出にも柔軟に対応できる点は大きな利点といえるでしょう。
住宅ローン控除の恩恵を受けやすい
住宅ローン控除は、年末時点の借入残高に応じて最大13年間の税額控除が受けられる制度です。頭金を少なくすると借入額が増えるため、控除額も大きくなりやすくなります。とくに初年度〜数年は税額控除の効果が実感しやすく、節税メリットを重視する方には大きなメリットとなり得ます。
デメリット
続いてデメリットも確認しましょう。
借入額が増える
頭金が少ないと、その分住宅ローンの借入額が増加します。とくに借入比率が物件価格の90%を超える場合、金利が上乗せされる金融機関が多く、結果的に総返済額が大きくなる傾向がある点には注意が必要です。毎月の返済負担に加え、返済期間全体の利息コストも膨らみやすく、家計への長期的な影響が大きくなります。
ローンの審査が厳しくなる
自己資金が少ない場合、金融機関側は返済能力や資金管理力をより慎重に見極める必要があり、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。希望通りの金額を借りられない可能性もあるため、事前に信用情報や返済比率を確認し、現実的な予算内で計画することが大切です。
売却時に担保割れする可能性が高くなる
頭金が少ない状態で住宅ローンを組むと、購入直後の残債が物件の市場価値を上回る「オーバーローン」状態になるリスクがあります。とくに返済初期は利息の支払いが多く、元本がなかなか減らないため、オーバーローンの状態が長引きがちです。
転勤や離婚などで早期に売却せざるを得ない場合、売却額でローンを完済できず、自己資金で差額を補う必要が生じる恐れがある点はよく理解しておきましょう。
注文住宅の頭金が多い場合のメリット・デメリット
続いて、頭金が多い場合のメリットとデメリットをそれぞれ整理して見ていきましょう。
メリット
頭金が多い場合の主なメリットは次の2つです。
借入額を抑えられる
頭金を多めに入れると住宅ローンの借入額を抑えられるため、月々の返済額や総返済額も軽減されます。利息負担も少なく済むため、長期的な家計の安定につながります。
とくに今後の金利上昇リスクを意識している方にとっては、金利変動の影響を最小限に抑える意味でも安心材料となるでしょう。
ローンの審査で有利になりやすい
頭金の額が多いと、金融機関からの信頼性が高まり、住宅ローンの審査が通りやすくなる傾向があります。自己資金の多さは「返済能力の高さ」や「計画的な資金準備ができている」ことの裏付けと見なされるためです。その結果、希望の融資額が承認される可能性が高まります。
デメリット
頭金を多く入れることで、次のようなリスクが生じる可能性もあります。
手元資金が減る
多額の頭金を入れると、現金の手持ちが大きく減ってしまうことがあります。予期せぬ出費やライフイベント(教育費、医療費、転職など)に対応できる余裕がなくなり、結果として生活に不安を感じる原因になる可能性もあります。
さらに、引っ越し費用やカーテン・家具・家電など新生活に必要な支出も見落とせません。一般的には生活費の6か月分程度の現金を残すのが安心とされており、頭金とのバランスをシミュレーションしておくことが重要です。
住宅ローン控除の控除額が少なくなる可能性がある
住宅ローン控除は年末残高に応じて控除額が決まるため、頭金を多く入れて借入額を抑えすぎると、その恩恵が限定的になることがあります。
とくに控除初年度の恩恵が小さくなりやすく、節税効果を重視したい方にとってはデメリットと感じやすくなるでしょう。
「頭金がたまるまで待つ」と「今すぐ買う」ならどっちがいい?
頭金をもっと貯めてから住宅購入するべきか、それとも低金利のうちに購入を決断すべきか。どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。ここでは、それぞれの選択肢のポイントと注意点を紹介しますので、判断のヒントにしてください。
頭金がたまるまで待つ場合のポイントと注意点
頭金を増やしてから購入するメリットは、借入額を抑えられる安心感にあります。しっかりとした貯金計画を立てられる方にとっては、精神的にも経済的にも無理のない選択といえるでしょう。
ただし、その間に住宅価格や金利が上昇するリスクがあるため、タイミングの見極めが重要です。インフレや土地価格の高騰、建築コストの上昇などで、貯金の増加より負担が大きくなる可能性があることは、よく理解が必要です。
今すぐ買う場合のポイントと注意点
今すぐ購入する最大の利点は、現在の金利水準や制度を活かせることです。今後金利が上昇すれば、たとえ借入額が同じでも返済総額は増えてしまいます。
また、住まいにかかる費用は家賃という形ですでに発生しており、将来の資産にならない支出が積み重なっていく点も見過ごせません。住宅ローン控除や贈与の非課税制度など、現行の制度を最大限に活用したい場合は、「今」という選択肢を選ぶことも検討しましょう。
「今の家計と価値観」を考慮し慎重に検討しよう
最終的に大切なのは、家族の収支バランスやライフプランに合った選択をすることです。たとえば、今の家賃に月1万円上乗せした程度でローン返済が可能であれば、今すぐの購入を検討する価値は十分あります。
一方で、将来の教育費や転職、介護など、ライフイベントに備える資金的余裕が必要な世帯もあるでしょう。「今が得か損か」ではなく、「いつが自分にとって適切か」を見極めることが、後悔のない家づくりにつながります。
「頭金」より「借入額」が重要!注文住宅は無理のない総額設計を
注文住宅の資金計画では「頭金はいくら用意すべきか」に注目しがちですが、本質的に重要なのは「いくら借りるのか」という借入総額のコントロールです。
ここからは、頭金にこだわりすぎず、無理のない総額設計を実現するためにできる工夫を紹介します。
補助金を活用する
住宅取得時には、国や自治体が用意する補助制度をうまく活用することで、自己負担を大きく減らすことが可能です。代表的な制度には、一定条件を満たす世帯に支給される「子育てグリーン住宅支援事業」「ZEH補助金」などが挙げられます(2025年5月現在)。
近年はとくに子育て世帯・若者夫婦世帯、また省エネ住宅への補助が充実していることが特徴です。なお、支援の内容や申請条件は年度ごとに変わり、また補助額上限に達した時点で閉めきられてしまうため、早めの情報収集が重要です。
補助金について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【2025年】注文住宅の補助金・助成金完全ガイド!減税制度や活用時のポイントも解説
親からの資金援助・贈与を活用する
両親や祖父母からの資金援助を受けられる場合は、「住宅取得資金の贈与非課税制度」を活用すれば、一定の条件を満たすことで最大1,000万円までが非課税となります。この制度を使えば、たとえば頭金に充当する形で借入額を抑えることも可能です。
贈与の話は切り出しにくい話題ですが、親世代にとっても相続税対策としてメリットを得られるケースも少なくありません。将来の家族資産を見据え、相談してみるのもよいでしょう。
建物・土地のコストバランスを見直す
予算内に収めるには、頭金の額やローンの組み方を考える前に、「土地と建物のどちらにどれだけ予算をかけるか」というバランスが重要です。
とくに注文住宅では、「好立地の土地に予算をかけすぎて、建物の質を下げざるを得なくなる」といったケースが後を絶ちません。そうした事態を避けるには、土地探しから建物設計・施工までを一括で管理できる「ワンストップ体制」の会社に相談し、土地+建物のトータルで資金配分を最適化するのがおすすめです。
家づくりをスタートする早い段階で、土地と建物を切り離さず「全体でいくらかかるか」を見える化し、無理のない資金計画を立てましょう。
まとめ
注文住宅の頭金は「多ければ安心」と思われがちですが、手元資金の余裕や今後の生活設計とのバランスも考慮する必要があります。大切なのは頭金の額ではなく、「最終的にどれだけ借りるか」という借入総額のコントロールです。
借入額を抑えるには、補助金制度の活用や親からの資金援助、土地・建物それぞれのコストバランスを見直すことが効果的です。ただし、どの手段が最適かは家庭ごとに異なるため、まずは現状を整理し、無理のない資金設計を立てることが重要です。
ポラスの「発見とちいえプラザ」では、土地探しから設計・施工、資金計画までをワンストップで支援しています。借入総額の圧縮にもつながるトータル提案が可能なので、資金に不安がある方も、まずは気軽にご相談ください。
SUPERVISOR
監修者